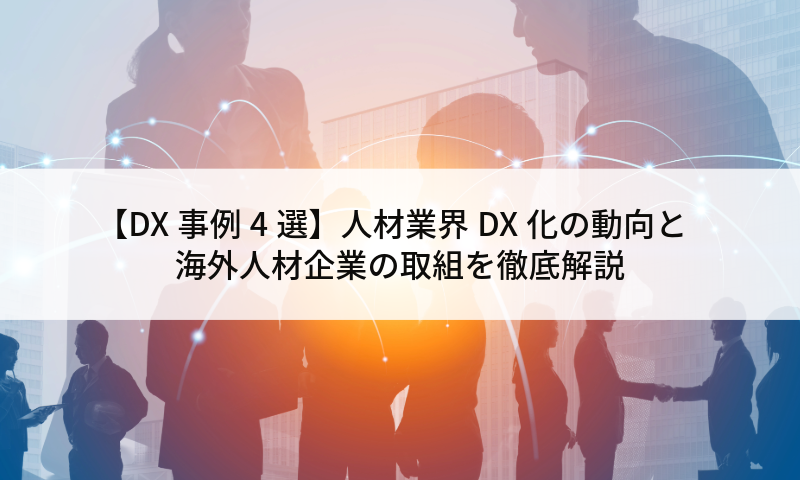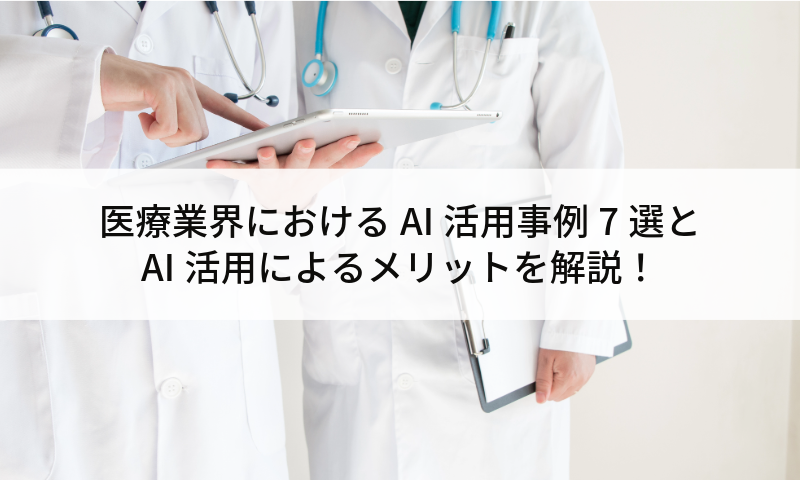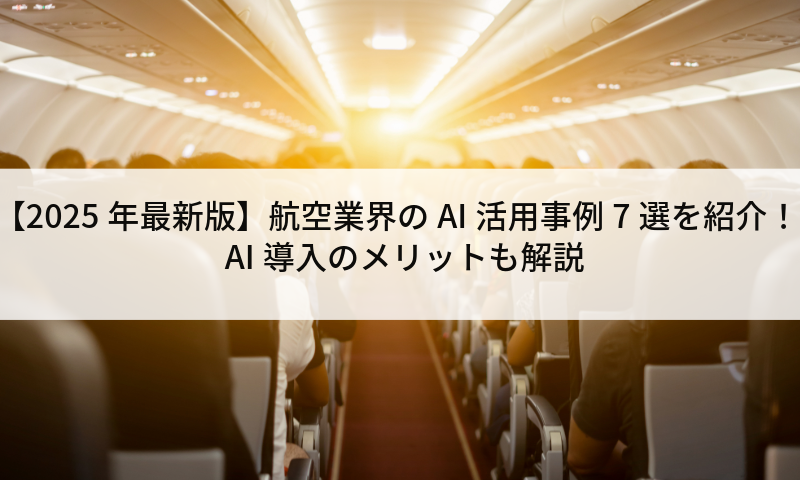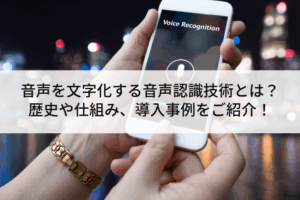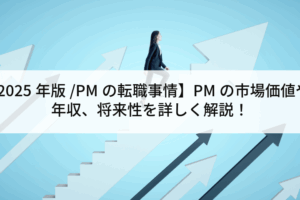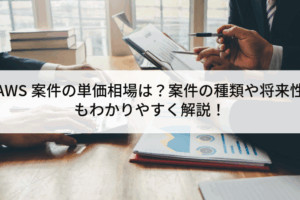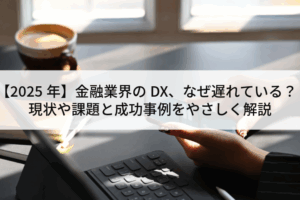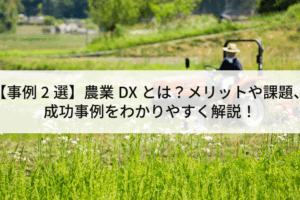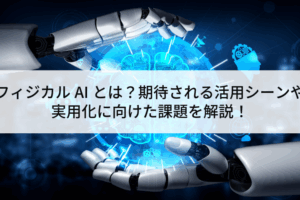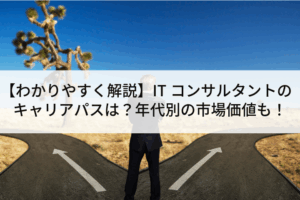AI技術の進化は、業務の効率化にとどまらず、仕事のあり方そのものを変えつつあります。
しかし今、多くの企業や自治体が直面しているのは、「AIを使いこなせる人材」の不足です。
この記事では、企業や自治体がどのようにAI人材を育成しているのか、その具体的な事例を4つ紹介します。
成功事例を通じて、育成体制のつくり方や教育のポイントを理解し、最適な人材育成の方向性を見つける手がかりを得られます。

目次
AI人材の育成が求められる背景を解説
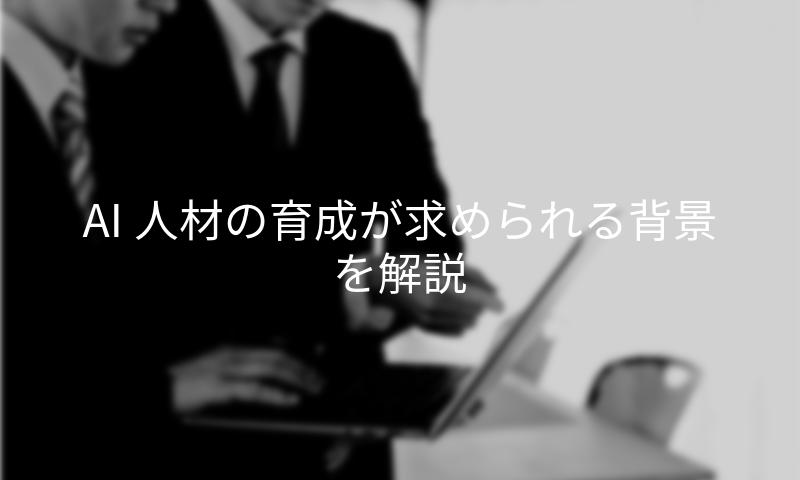
AI人材の育成が求められる背景には、急速に進化する技術に対して、人材の供給が追いついていない現状があります。
情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2025」によると、DXを推進する人材が「やや不足」「大幅に不足」と回答した企業が85.1%に上りました。
2022年度調査(83.5%)からほとんど改善が見られず、社会全体でAI人材の不足が恒常化しており、企業の競争力低下が懸念されます。
AI人材が不足する背景には、教育・採用・社会構造の課題が複雑に絡み合っています。
AI分野では高度な専門知識が求められる一方で、それを体系的に学べる教育環境はまだ十分に整っていません。
その結果、実践的なスキルを持つ人材が育たず、企業間での人材獲得競争が一層激しくなっています。
特に資金力のある大手企業に人材が集中し、中小企業や自治体は採用・育成の両面で不利な立場に置かれているのが実状です。
さらに、少子高齢化によって労働人口が減少しており、長期的にもAI人材の供給が増えにくい状況です。
このようにAI人材の育成が求められる背景には、教育体制の遅れや人材獲得競争の激化などの要因が関係しています。
今後、企業や自治体が持続的に成長するためには、AIを理解し活用できる人材を計画的に育成する取り組みが欠かせません。
参照:
・「”DX動向2025″データ集」IPA
・「AI人材とは?育成の注意点と必要なスキル・不足する理由を解説」スキルアップAI Journal
・「AI人材とは?不足している理由や必要なスキルを解説」Schoo for Business
・「AI人材はいらない?理由や経済産業省が行う人材不足の解決方法」ディジタルグロースアカデミア
社会が必要とするAI人材を解説
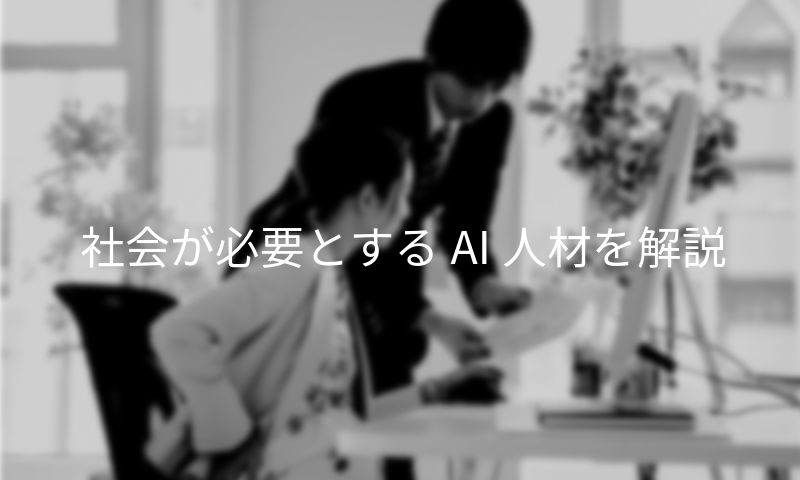
社会がいま必要としているAI人材とは、生成AIを使いこなすだけでなく、AIを活用して新たな価値を生み出し組織変革を進められる人です。
生成AIの普及により、知識や定型業務の多くをAIが補う一方で、人間にはAIに代えられない創造的な力を磨き上げる必要があります。
特に重要なのは、リーダーシップや批判的思考といったパーソナルスキル、そして事業やサービスを構想するデザインスキルです。
さらに「問いを立てる力」や「評価・選択する力」も欠かせません。
AIの回答をそのまま受け入れるのではなく、課題を自ら発見し、仮説を立てて検証しながら最適解を導く姿勢が必要です。
その際、AI技術の背景や倫理的側面を理解し、社会的影響を踏まえて判断する視点も求められます。
また、AIを有効活用するためには、AI技術だけでなく業界や組織の課題について深く理解している必要があります。
自社のビジネスや業務プロセスを熟知し、データを整理・統合してAIが成果を発揮できる環境を整える「データの目利き」も重要です。
このように今後も必要とされるのは、生成AIなどの新技術をいち早く取り入れるだけでなく、人とAIの協働によって新しい価値を創出できる人材です。
参照:
・「”生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024″~変革のための生成AIへの向き合い方~ を取りまとめました」経済産業省
・「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024 (令和6年6月)<概要>」経済産業省
・「生成 AI 時代の DX 推進に必要な人材・スキルの考え方 2024 ~変革のための生成 AI への向き合い方~」経済産業省
AI人材育成事例を紹介

ここからは、先行事例を知って自社に落とし込みたいという方のために、実際にAI人材の育成を行った4つの企業や自治体の取組みを紹介します。
● KDDI株式会社:従業員向けKDDI AI-Chatの展開
● 神戸市役所:市役所職員の生成AI利活用の推進
● 文部科学省:リーディングDXスクール 生成AIパイロット校の取り組み
株式会社日立製作所:AIエージェントの提供
株式会社日立製作所(以下、日立)は、生成AIを安全かつ効果的に活用するため、2023年に「Generative AIセンター」を設立しました。
同センターでは、生成AIのリスクを多面的に検討した業務利用ガイドラインを策定し、業界の変化に合わせて継続的に更新しています。
さらに、社員向けの相談窓口を設け、利用ルールだけでなく現場で生じる疑問や課題にも柔軟に対応しています。
また、Microsoftが提供しているAzure OpenAI Serviceを活用した「Generative AIアシスタントツール」を社内に導入。
議事録の自動生成や資料作成支援、システム開発の効率化などを通じて業務全体の生産性を高めました。
こうした取り組みにより、社員のAIリテラシーは向上し、ノウハウが積み重なっていきました。
そしてグループ内の数百件に及ぶ事例で得た知見やノウハウをもとに、日立は新たなビジネス「AIエージェント」を展開しています。
AIエージェントは、企業の業務内容や課題を理解し、自動で調査や文書作成、情報整理などを行う業務支援サービスです。
社内での実績をもとに、最短1日で試験導入が可能な環境を整備し、各社のニーズに応じて本格運用へとスムーズに移行できます。
日立は、社内実装で培った技術と運用ノウハウを外部にも展開することで、AIを軸としたビジネス価値の創出と人材育成の両立を目指しています。
参照:
・「ニュースリリース」日立
・「日立、数百の事例で獲得したOTナレッジの活用手法によりお客さま専用のAIエージェントを迅速に提供」日立
KDDI株式会社:従業員向けKDDI AI-Chatの展開
KDDI株式会社(以下KDDI)は、2023年5月に社内向けAIチャットサービス「KDDI AI-Chat」を導入しました。
同サービスは、社内ガイドラインと厳格なセキュリティ基準に基づいており、社員が安心して生成AIを使える環境を提供しています。
導入後はリサーチや資料作成といった定型業務に加え、思考整理や新規事業のアイデア創出など、より創造的な領域にも利用が広がりました。
さらにKDDIは、生成AIチャットをMicrosoft Teams上で使用できる「KDDI AI-Chat for Teams」を開発。
スマートフォンやグループチャットからAIを呼び出せることで、業務効率の向上と、社員が日常業務を通じてAIスキルを磨ける仕組みの両立を実現しています。
そしてサービス開発と並行して、AIを安全に使うための教育コンテンツの作成や、講師によるトレーニングも実施。
倫理的なAIの扱い方や、業務への具体的な活用方法を学ぶ機会を設けることで、社員一人ひとりのリテラシー向上に繋げています。
こうした取り組みを通じて、KDDIは単にAIを「使う」だけでなく「業務に活かす」人材が育ちやすい環境を整え、今後はAIを積極的に活用したビジネスを進めていくでしょう。
参照:
・「社員1万人が”KDDI AI-Chat”の利用を開始」KDDI株式会社
・「KDDI AI-Chatの内製開発の取り組み」KDDI Tech note
神戸市役所:市役所職員の生成AI利活用の推進
神戸市役所(以下、神戸市)は、AIの安全性を確保しながら、行政における活用を積極的に進めています。
2023年6月から9月にかけて、職員133名を対象にChatGPTの試行利用を実施しました。
多様な職種の職員が参加したことで幅広い活用アイデアを収集でき、行政事務において業務の効率化と質の向上を確認しています。
一方で、より多くの職員が使いやすい仕組みづくりなど、機能面やサポート面の課題も明らかになりました。
試験利用の結果を踏まえ、神戸市はAIを安全に活用するためのルールとして「神戸市におけるAIの活用等に関する条例」を制定しました。
さらに、その運用を支える「神戸市におけるAIの活用等に関する基本指針」を定め、リスク評価や機密情報の管理基準を明確にしています。
2024年2月からは生成AIの本格利用を開始し、全職員がMicrosoft社の「Copilot」を利用できる環境を整備しました。
併せて「神戸市生成AI利用ガイドライン」や「プロンプト事例集」を作成し、AIの利用に不安を感じる職員にも安心して活用できるサポート体制を整えています。
これらの取り組みにより、神戸市は行政の信頼性を保ちながら、生成AIによる業務改革と人材育成の両立を進めています。
参照:
・「生成AIの利活用」神戸市
・「AI条例の制定と利活用」神戸市
文部科学省:リーディングDXスクール 生成AIパイロット校の取り組み
文部科学省は令和5年7月から全国の学校を対象に「生成AIパイロット校」を指定し、教育現場での生成AIの活用にむけた取り組みを進めています。
教育活動や校務でのAI活用を実証的に検証し、全国で共有できる知見を蓄積することが目的です。
例として東京都八丈町立富士中学校では、教員の業務効率化をテーマに、学習指導案や時間割の作成などに生成AIを導入。
学習指導案について作成時間は約90分から30分に短縮され、完成度もAIで6〜8割を満たすなど、生産性と品質の両面で効果が確認されています。
時間割の作成では、教員の担当や教室の利用状況といった条件をAIに入力することで、従来数時間かかっていた3学年分の週次時間割を短時間で自動生成できました。
さらに同校では、全教員を対象としたAI活用研修も開催。
この研修では、参加者全員が具体的な活用イメージを得たほか、生徒の授業でもAIを使った課題づくりが進められています。
こうした実践は、文部科学省が目指す「教育の質の向上」と「働き方改革」の両立に向けたモデルケースとなり、今後は生成AIを活かした教育環境の整備が全国に広がっていくでしょう。
参照:
・「リーディングDXスクール生成AIパイロット校」リーディングDXスクール
・「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」文部科学省
・「リーディングDXスクール事業【AIパイロット校】」文部科学省
まとめ

この記事では、AI人材育成が急務とされる背景から、実際の企業や自治体の具体的な成功事例までをご紹介しました。
これらの事例から共通して見えてくるのは、「安全な利用環境の整備」と「実践を通じてリテラシーを高める教育」が、AI人材育成の鍵であるということです。
特に、日常業務にAIを組み込むことで、社員や職員が自然とスキルを習得できる仕組みづくりが重要です。
● まだ仕事を受けることは考えていないけど、どんな案件があるのか知りたい
● 働く場所にとらわれずリモートでできる案件を探したい
フリーランス向けのフルリモート案件をお探しの方へ

✔高単価案件多数
150万円以上の案件が80%以上、200万円以上も!
✔フルリモート案件多数
リモートで完結するDX・戦略案件が見つかる
✔上場企業や優良企業から直接スカウトが届く
簡単なプロフを見てみる