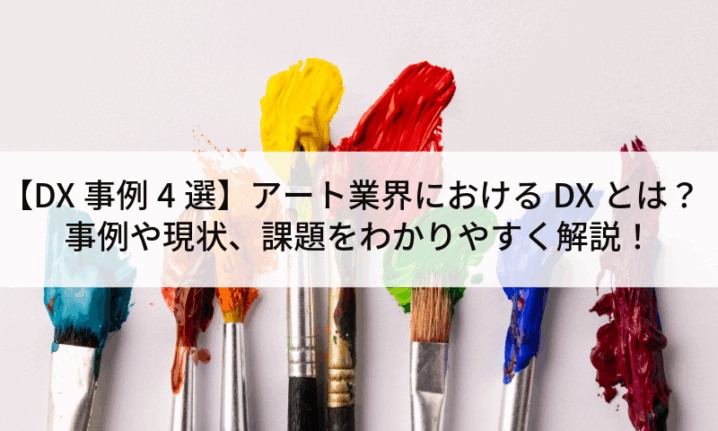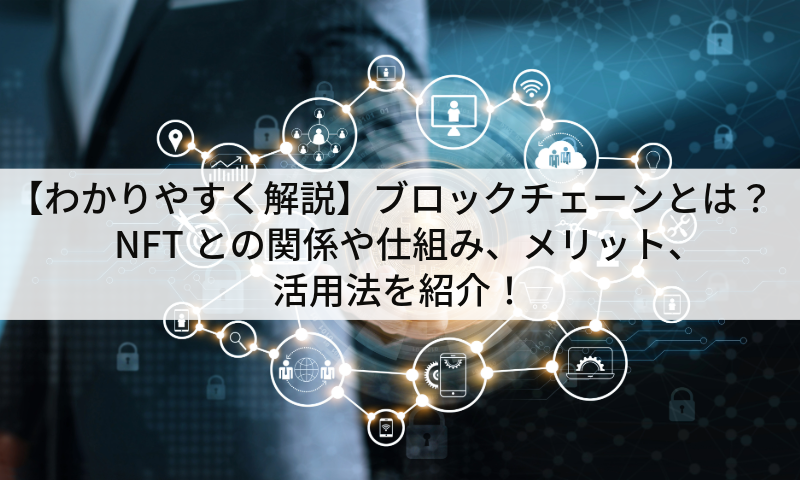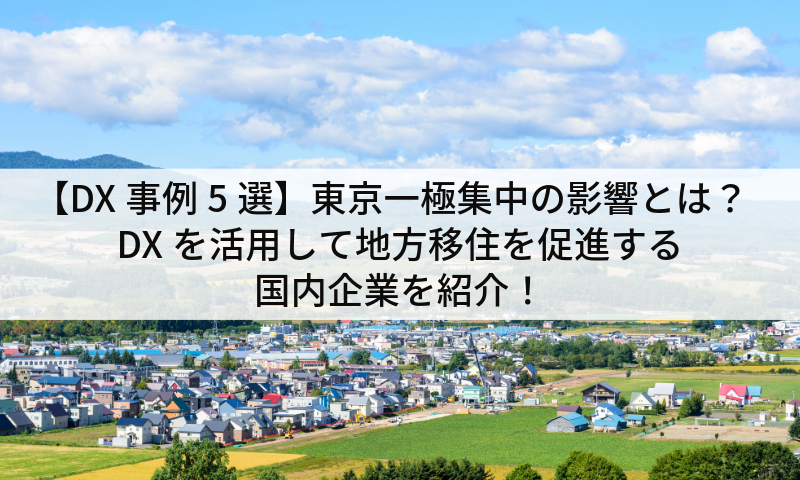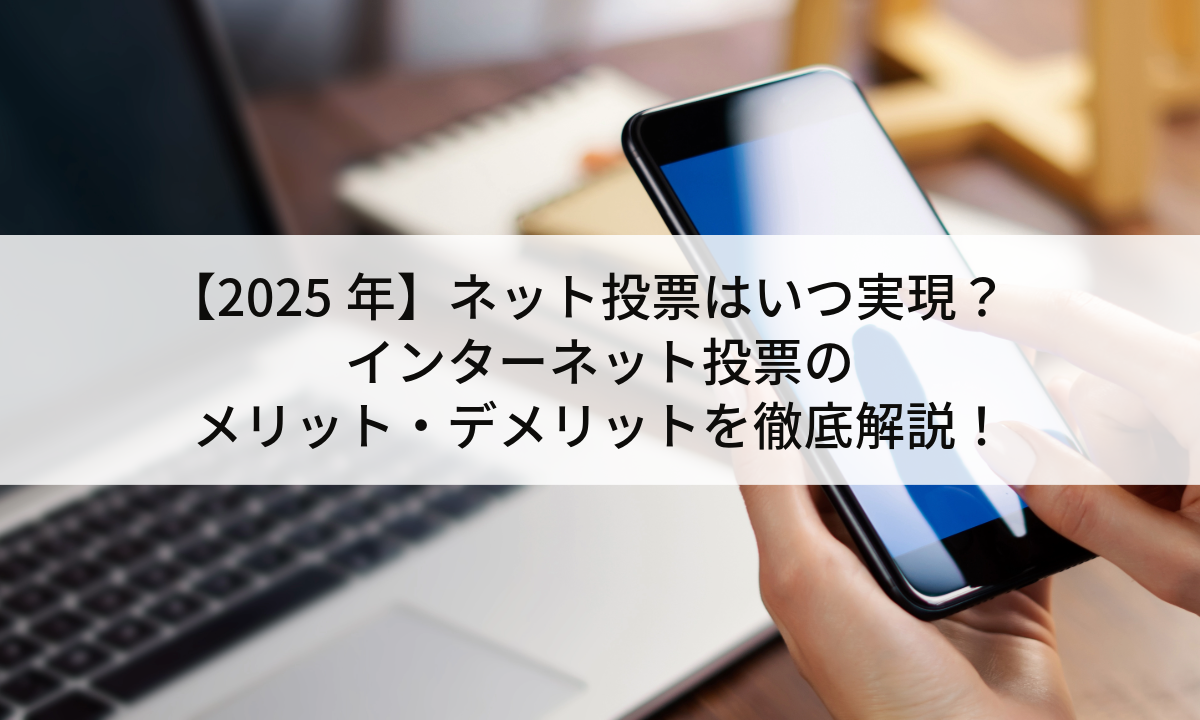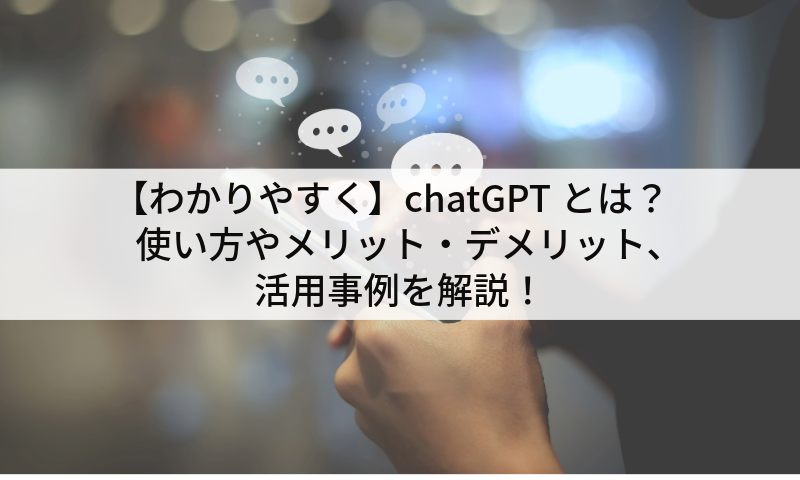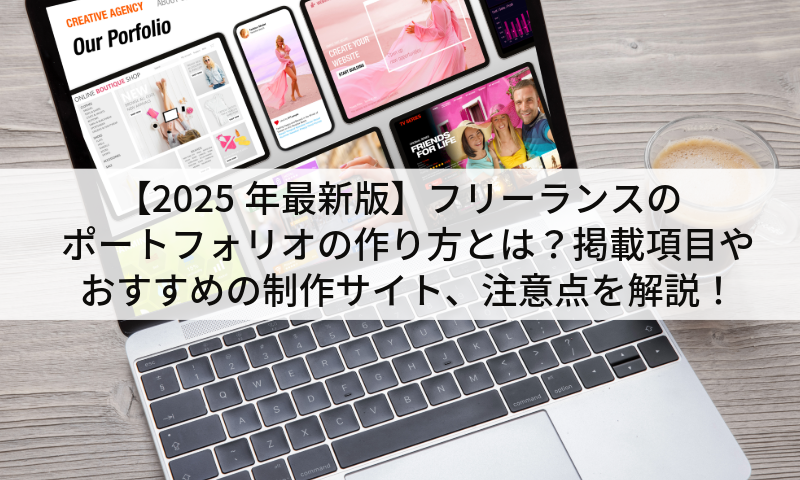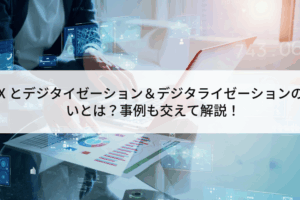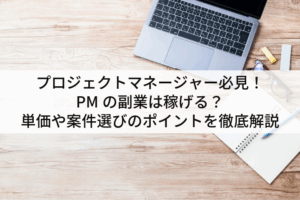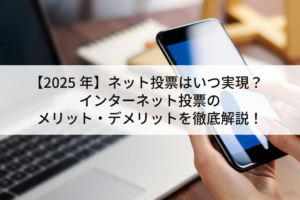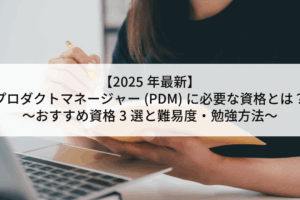本記事ではアート業界におけるDXの事例やその背景、現状と課題を解説します。
アート業界において、DXがどのように取り入れられていくのか知りたい方は参考にしてみてください。
日本でもアートにまつわる課題解決と、アートが持つ価値を活かすためにDXの導入が進んでいます。
具体的な事例も紹介しますので、順番に見ていきましょう。
目次 アート業界におけるDXとは、DX化によって、アートを取り巻く分野において課題を解決したり、文化的な価値を活かしたりして、社会にもたらす価値を最大化することです。 インターネットの普及や感染症の拡大などを受けて、より多くの人が芸術を鑑賞できるようになることや、美術館の業務効率化などが求められており、様々な法改正を受けてDX化が進んでいます。 このようなアート業界におけるDX化を「アートDX」と呼ぶ場合もあります。 参照: 次にアート業界においてDX化が進められることとなった背景を解説します。 どのような法改正を経て、アート業界におけるDX化が進むようになったのか、参考にしてみてください。 アート業界におけるDX化が進められるようになった理由として、2017年に行われた文化芸術基本法の改正があります。 同法の改正によって、以下の第2条第10項が新設されました。 第2条第10項 同項には、文化芸術単体での発展だけでなく、観光やまちづくり、国際交流、福祉などの関連分野と連携してアートに関する施策を進めなければならないと規定されています。 広い分野と連携して発展を進めていくよう求められたことと、社会全体としてDX化を推進する流れが登場したことを受けて、アート業界においてもDX化の重要性が高まりました。 参照: 文化芸術基本法の改正に次いで、2022年に行われた博物館法の改正もアート業界におけるDX化の流れに関与しています。 2022年に同法に第3条第1項第3号が新設され、博物館が行うべき事業として電磁的記録(デジタルアーカイブ)を残し、公開することが明記されました。 これまで博物館の事業としてデジタルアーカイブの作成は明記されていませんでしたが、インターネットの普及を受け、今回の改正で博物館の事業として明確に位置付けられることとなりました。 デジタルアーカイブを作成し、公開することで、実際に足を運ぶのが難しい人でも作品を閲覧できるため、アートのさらなる活用につながることが期待されています。 参照: ここからはアート業界においてDX化が進むことでどのようなことが実現できるのかを紹介します。 それぞれ順番に見ていきましょう。 美術館にオンラインの予約システムを設けることで、混雑緩和や待ち時間の短縮、受付業務の効率化につながります。 利用者は予約専用サイトから事前に来館時間が設定されたチケットを購入し、時間が近づいたら来訪してもらうことで、館内に人が滞留せず、鑑賞する人の分散が可能です。 また、チケットの発券や会計などの業務が効率化されるため、コスト削減にもつながります。 参照: 文化資源をデジタルアーカイブとして記録し、公開することで作品や資料の保存と体系化、多様な創作活動への活用につながります。 また、新型コロナウイルスのような感染症が流行した際に、直接足を運んで作品を鑑賞することが難しくなっても、デジタルアーカイブを公開することで、作品の閲覧が可能です。 参照: バーチャルミュージアムは、インターネットを通じて誰でも場所や時間を問わず、展示物を鑑賞できるオンライン上の美術館です。 オンライン上で展示室の回遊や、学芸員による作品解説、作品のダウンロードといったコンテンツを楽しめます。 感染症流行時の対応以外に、海外や遠方に住んでいる人や障害を持っている人でも芸術作品に触れられるため、アートを身近に感じてもらいやすくなります。 参照: 続いて、アート業界におけるDXの取り組み事例を4つ紹介します。 前章で紹介したことをはじめ、実際にDX化を進めている美術館の事例を取り上げるので参考にしてみてください。 それぞれ順番に見ていきましょう。 東京都の三の丸尚蔵館では、1993年11月から2020年9月まで自館で開催した計86回の展覧会の図録をデジタルアーカイブにして、インターネット上で公開しています。 これらはダウンロードも可能で、資料だけでなく、作品解説や展覧会のテーマに沿った論文やコラムなどのコンテンツも併せて公開されています。 デジタルアーカイブの作成は、紙媒体をスキャンすることによってPDF化しており、スキャンにあたっては、ページに影が入らないよう専門の委託事業者の手を借りたようです。 公開されているのは、全てのページをそのままスキャンした保存用と、作品ごとの画像利用規定に準じて一部加工を施し、各作品へ簡単に遷移できるようリンクを設けた公開用、作品群ごとにファイルを分割したものの3つがあります。 参照: 東京都美術館で2021年に開催された「吉田博展」では、新型コロナウイルス流行下での開催であったため、バーチャルツアーができるよう専門の事業者とタイアップしました。 館内の撮影やバーチャルミュージアムの制作、ホームページへの掲載など一式を委託したようです。 バーチャルミュージアムでは館内を自由に回遊できるほか、画像も高画質なため、拡大すれば作品の細部まで鑑賞できる状態で公開されました。 参照: ベネッセアートサイト直島では、インバウンドを含めた観光客の増加に対応するために、2024年10月1日からオンラインチケット対象施設を拡大しました。 全てのアート施設でオンラインチケットを導入し、チケットと連動した公式アプリをリリースすることで、利便性にも配慮しています。 これによって利用者は事前に日時指定のオンラインチケットを購入し、指定された時間に施設を訪れることで、待ち時間を短縮し、混雑緩和にもつながっています。 参照: デジタル技術を活用した没入感の高い新たなアートの形態として、2024年にベルサール新宿南口で開催されたImmersive Museum TOKYOが挙げられます。 こちらでは、壁や床一面に絵画の世界が投影され、室内に流れる音楽とともにアートの世界を全身で体感できます。 観るだけではない新たな鑑賞体験を提供する展覧会として話題になりました。 参照: 最後にアート業界におけるDX化の現状を解説します。 アートDXは、法改正や取り組み事例など様々な分野で動きを見せていますが、現状には課題やNFTといった新たな技術の登場なども起こっています。 それぞれ詳しく見ていきましょう。 文部科学省によると、日本のアート市場は世界全体において、1%しか占めていません。 その売上規模は946億5,900万円(6億8,100万ドル(令和5年12月26日告示の財務官支出レートより1ドル139円で計算))と推定されており、世界第8位の市場規模です。 アート市場は、上位の数ヵ国で市場の大半を占めているのが実情です。 令和5年5月5月の観光立国推進閣僚会議では、当時の首相が日本のアート市場をさらに押し上げるため、国際的なアートフェアの誘致等にも取り組んでいくと発言しています。 そのため、今後も国を挙げてアート分野の成長に向けた取り組みが行われると予想されます。 参照: デジタルアートと親和性が高いのがNFTです。 NFTは、ブロックチェーン技術によってコピーが容易なデジタルデータにおいて所有権や唯一性を確保することができます。 そのため、デジタルアートと相性が良いです。 画像や音声データにブロックチェーン技術を組み合わせることで、所有者を明確にできるため、売買や資産管理などのデジタルアートの運用や、経済の活発化につながると期待されています。 参照: 文部科学省が2020年に行った調査によると、博物館の資料におけるデジタルアーカイブ化を実施しているのは24.4%に留まります。 実施を検討している館を含めても50.8%と約半数です。 また、デジタルアーカイブに関する専門知識を持った職員を配置していない館は73.4%と多くを占めており、資料や資料目録のデジタル化を進められないことが課題となっています。 参照: 今回はアート業界におけるDXとはどのようなものか、具体的な事例や現状・課題を交えて解説しました。 芸術分野においても、ビジネスとはまた違った視点からDX化が進められています。 ただ、ビジネス分野においてもDX人材が不足しているように、アートDXも人材難により進められていない部分があります。 今後あらゆる分野において、DX人材の需要はさらに高まっていきそうです。 Contact EARTH matchingには、大企業や官公庁など信頼性の高いクライアントからの高単価案件が豊富に掲載されています。 アート分野をはじめ、社会課題をDX推進によって解決したいと考えるフリーランスエンジニアの方の参画をお待ちしています。 無料で今すぐ行えるエキスパート登録を行って、案件にアサインしてみてください。 ✔高単価案件多数
地方在住で参画できるフルリモート案件や、大企業のDX化を推進する案件も扱っていますので、無料エキスパート登録を行い案件を探してみてください。
アート業界におけるDXとは
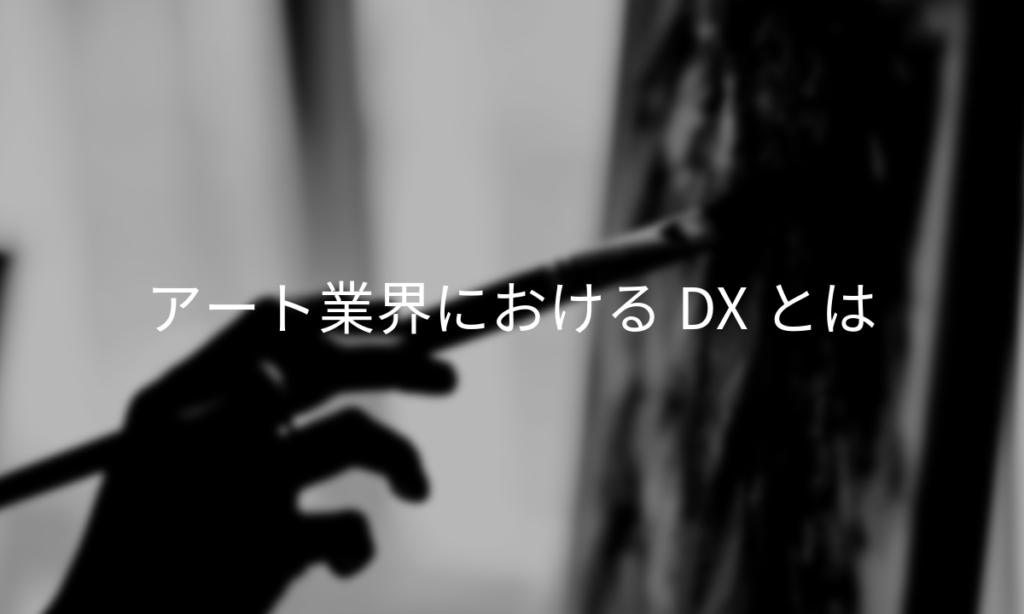
・「アートDX基金」東京藝術大学未来寄附金アート業界におけるDX化の背景
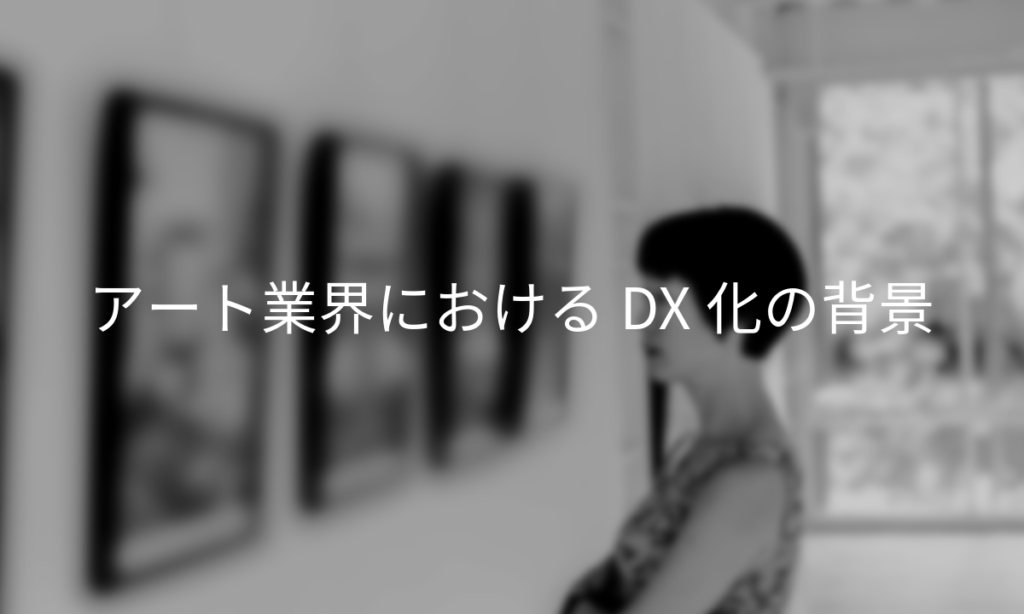
文化芸術基本法の改正(2017年)
文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。
(引用:文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号) e-GOV法令検索)
・「【日本総合研究所が描く未来 vol.3】文化芸術分野のDXで、博物館の新たな価値創造と観光振興を支援」三井住友フィナンシャルグループ DX-link
・「文化芸術基本法」文化庁
・「文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
・「資料① 文化芸術推進をめぐる社会環境の変化」東京都町田市博物館法の改正(2022年)
・「【日本総合研究所が描く未来 vol.3】文化芸術分野のDXで、博物館の新たな価値創造と観光振興を支援」三井住友フィナンシャルグループ DX-link
・「法改正で変わる日本の博物館」文化庁 博物館総合サイト
・「博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索アート業界におけるDXでできること
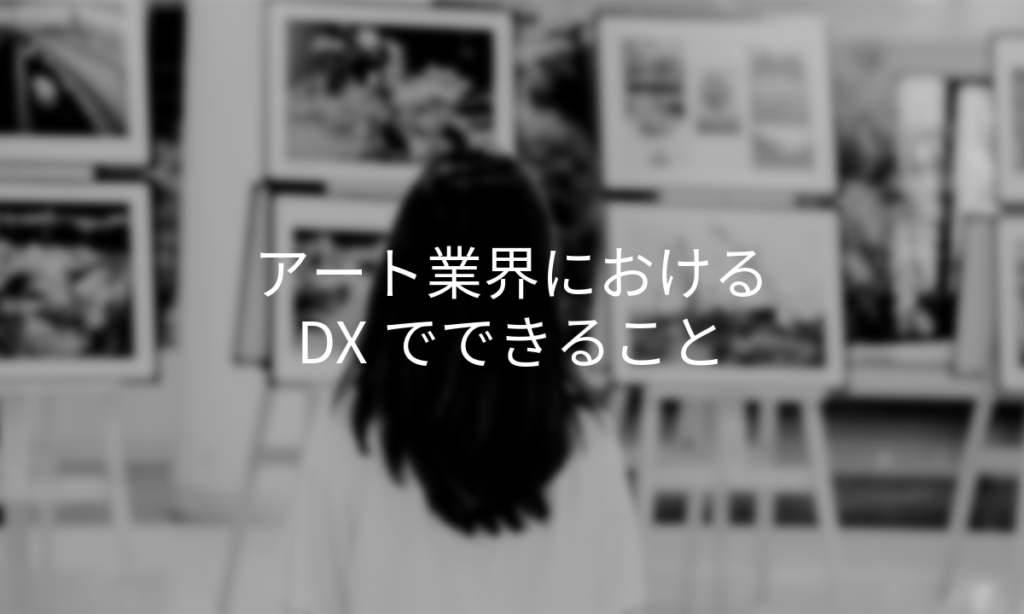
● デジタルアーカイブ化
● バーチャルミュージアム予約システム
・「美術館・博物館のDX化|変わる時代に変わらない感動を」bizlyデジタルアーカイブ化
・「博物館資料のデジタル・アーカイブ化の目的・状況について」文化庁
・「デジタルアーカイブ日本の芸術・文化を残し、活かす」立命館大学 立命館大学研究活動報バーチャルミュージアム
・「バーチャルミュージアム」公益財団法人土岐市文化振興事業団 土岐市美濃陶磁歴史館
・「バーチャル・ミュージアム」 大日本印刷株式会社 artscapeアート業界におけるDXの取組事例
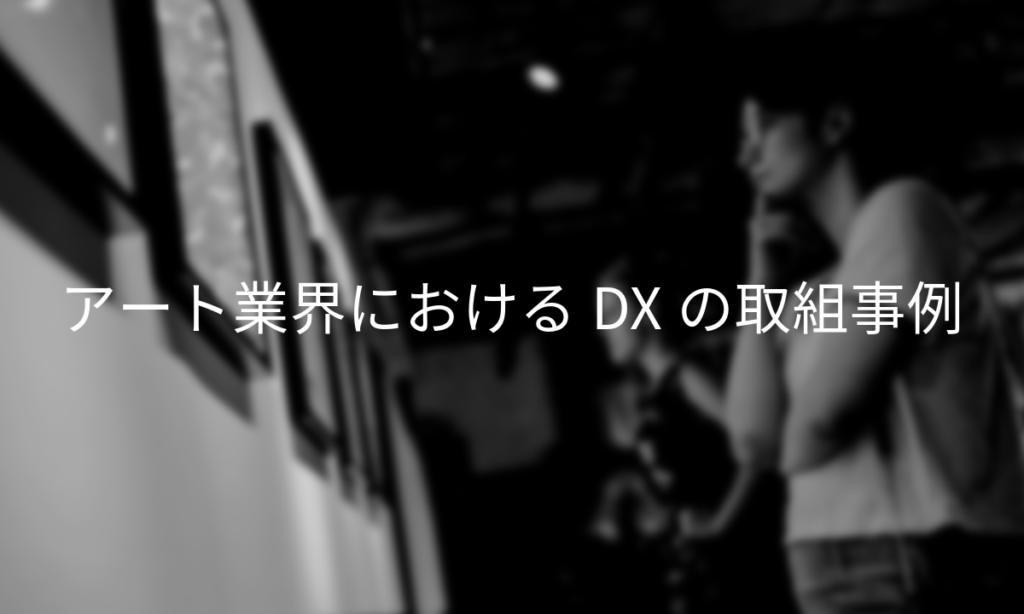
● 東京都美術館
● ベネッセアートサイト 直島
● Immersive Museum TOKYO三の丸尚蔵館
・「デジタルアーカイブ社会におけるミュージアムの収蔵品検索―三の丸尚蔵館収蔵品検索サイトの構築を通して―」皇居三の丸尚蔵館
・「展覧会図録のデジタルアーカイブとその公開──三の丸尚蔵館の事例から」大日本印刷株式会社 artscape東京都美術館
・「【事例】あの東京都美術館をバーチャルツアーで制作!映像のシステムや活用方法まで徹底解説」株式会社Advalayベネッセアートサイト 直島
・「10/1より直島・豊島・犬島の全アート施設でオンラインチケットを導入」株式会社ベネッセホールディングス ベネッセアートサイト直島
・「ベネッセアートサイト直島の全施設オンラインチケット(一部除く)での運用開始(2024年10月1日より)」note Joh’s GuideImmersive Museum TOKYO
・「vol.3 印象派と浮世絵」Immersive Museum TOKYO
・「新感覚のアート没入体験「イマーシブミュージアム」が開催。“AIゴッホ”で肖像画体験も」株式会社電通広報局 電通報アート業界におけるDXの現状
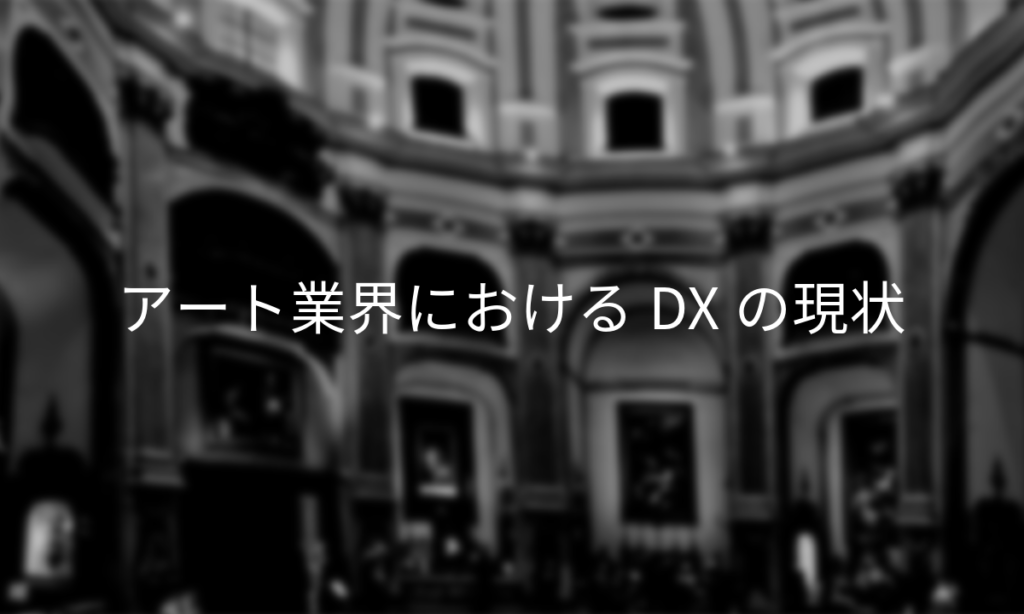
市場規模
・「日本のアート市場の規模等に関する調査分析レポート「The Japanese Art Market 2024」を公開」文化庁NFT
・「アートは「共有する」時代。DXで変革を遂げるアート購入事情に迫る」株式会社デジタルホールディングス DIGITAL SHIFT TIMES
・「美術品の保管、展示、寄贈について」NFT鳴門美術館DX化への課題
・「博物館資料のデジタル・アーカイブ化の目的・状況について」文化庁まとめ
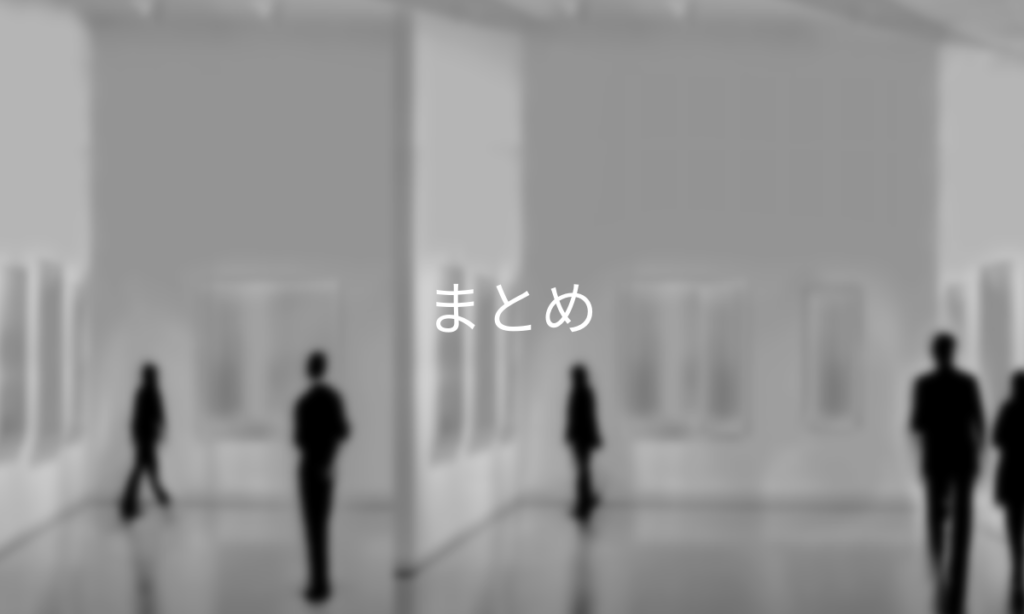
フリーランス向けのフルリモート案件をお探しの方へ

150万円以上の案件が80%以上、200万円以上も!
✔フルリモート案件多数
リモートで完結するDX・戦略案件が見つかる
✔上場企業や優良企業から直接スカウトが届く
簡単なプロフィールを登録し、あとはスカウトを待つだけ