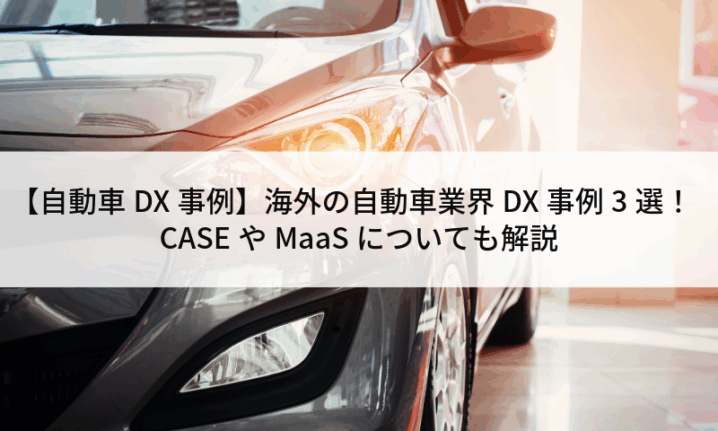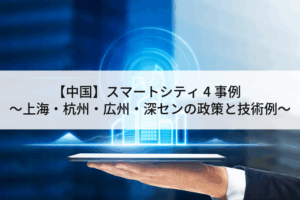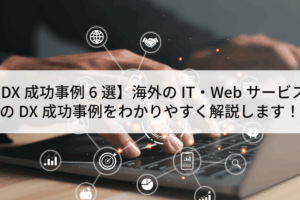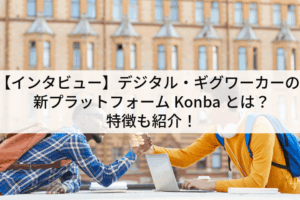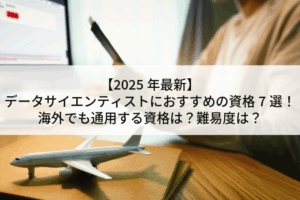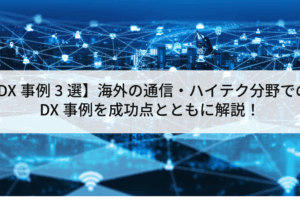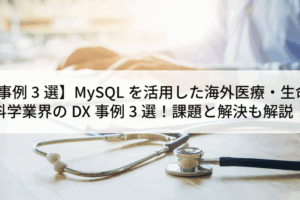新型コロナウィルスの影響を受け、日本・欧州の新車販売台数は2020年・2021年ともに落ち込みを見せています。
その一方で、感染リスクを減らせる自動車の利用ニーズは増え、中古車の価格が高騰しているという現実もあります。
新型コロナウイルスの影響も落ち着いてきた2024年度は新車、中古車ともに前年越えの販売量となっており、需要が高くなっています。
かねてから、海外の自動車業界が先んじて取り組んできたDXですが、感染拡大を契機に日本でもDX導入の動きが進むものと予想されます。
この記事では、海外の自動車業界におけるDX事例をご紹介するとともに、自動車業界のDXを語る上で欠かせない要素である「CASE」や「MaaS」についても解説します。
参照:
・「2021年の世界新車販売、米中プラスも低水準 半導体不足でなお先行き不透明」日刊自動車新聞
・「2024年度の国内新車販売、3年連続前年超え」一般社団法人 日本自動車会議所
・「2024年度の中古車登録・届け出台数」一般社団法人 日本自動車会議所
目次
自動車業界DXのトレンド

自動車業界全体で取り組むDXは、具体的には以下の2つの概念で説明することができます。
・CASE
・MaaS
以下、それぞれの概念について、かんたんにご説明します。
CASEとは
CASEというのは造語であり、以下4つの単語の頭文字をもとに作られています。
● Autonomous(自動運転)
● Shared&Service(シェアリング・サービス)
● Electric(電動化)
自動車自体の進化とともに、自動車を取り巻くサービスの形態も進化することを提唱したもので、自動車業界の目指す方向性を示す概念として認知されています。
C:Connectedとは
CASEのCにあたる「Connected」とは、日本語に直訳すると「接続された」という意味になります。
自動車にIoT技術を融合させることで、車や周辺状況・道路状況などの取得データを活用するだけでなく、車内でより快適に過ごすための機能を活用できるようになります。
具体的な事例として、トヨタ自動車のコネクテッドサービス「T-Connect」を見てみると、以下のようなサービスが確認できます。
・動画、音楽などの大容量コンテンツを車内Wi-Fiで楽しめる
・事故や急病、あおり運転などで困った際に、車内オペレーターが消防、警察に出動を要請できる
通信機能を活かしたサービスは、今後も新しいものが登場するものと予想され、ドライバーの乗車体験の向上につながることでしょう。
インターネットを介したバーチャルな空間を使って、多彩な自動車を紹介・販売するようなアプローチも考えられます。
A:Autonomousとは
CASEのAにあたる「Autonomous」とは、日本語で「自動化(自動運転)」の意味合いで用いられます。
一口に自動運転といっても細かい条件があり、以下のようなレベルに応じて区分されています。
| レベル | 概要 | 運転操作の主体 |
| レベル0 | 【運転自動化なし】
自動運転する技術が何もない状態。 |
運転手 |
| レベル1 | 【運転支援車】
システムが、以下のどちらかを部分的に行う ・アクセル、ブレーキ操作 ・ハンドル操作 |
運転手 |
| レベル2 | 【運転支援車】
システムが、以下の両方を部分的に行う ・アクセル、ブレーキ操作 ・ハンドル操作 |
運転手 |
| レベル3 | 【条件付自動運転車(限定領域)】
決められた条件下で、すべての運転操作を自動化する ※(運転自動化システムが作動している間も、システムからの要請で運転手はいつでも運転に戻れなければならない) |
システム
※(システムが作動していない場合は運転手) |
| レベル4 | 【自動運転車(限定領域)】
決められた条件下で、すべての運転操作を自動化する |
システム |
| レベル5 | 【完全自動車運転】
条件なしで、すべての運転操作を自動化する |
システム |
日本国内では、市販のレベル3の自動運転車が公道を走ることが認められており、2022年にはレベル4の自動運転車の公道走行を許可する道路交通法の改正案が閣議決定されています。
海外に目を向けると、ドイツでは世界で初めてレベル4の自動運転が解禁されており、将来的には各国で高レベルの解禁が進むものと推察されます。
レベル5の自動運転が認められれば、例えば目的地まで1泊2日で移動するキャンピングカーのように、ぜいたくな寝台車両の運行サービスなども実現できるかもしれません。
自動運転の普及にともない、これまで自動車メーカーが想定してきた付加価値の概念が、大きく変わることでしょう。
CASEのSにあたる「Shared&Service」には、カーシェアや配車サービスなどの「シェアリング・サービス」などが該当します。
日本でも広く知られているUber Eatsは、もともとアメリカで誕生した配車サービスのUberから派生したサービスで、シェアリング・サービスの一つに数えられます。
日本でも、2024年3月から「日本版 ライドシェア」を一部地域で導入し始めました。
東京をはじめとする大都市では、タクシーに対して「見つかりにくい」・「つかまりにくい」などの不満を持っている利用客も少なくないため、将来性は高い分野の一つと言えるでしょう。
E:Electricとは
CASEのEにあたる「Electric」は、日本語で「電動化」のニュアンスとなり、いわゆる電気自動車の分野が該当します。
日本国内でも日産・リーフなどの優秀な電気自動車が登場しており、航続距離は450km以上となっています。
世界各国で環境規制が厳しくなる中、ガソリン車・ディーゼル車などの内燃機関車が、将来的に禁止の方向へと進む流れは避けられないものとなるでしょう。
そこで代替案となるのが、走行中のCO2排出を減らすことができる電気自動車です。
電気自動車は、自動車としての性能に加えて、停電時に非常電源として利用できるなどのメリットもあります。
0-100km/h加速のタイムが3.3秒の「テスラ・モデル3」など、電気自動車でありながらポルシェ顔負けの加速を実現しているものもあり、今後の成長が期待される分野です。
MaaSとは
CASEを進化させた先にあるステージ、車も含めた「各種交通機関を使って移動する」ことが一つのサービスになったものを「MaaS(Mobility as a Service)」といいます。
MaaSを利用することで、バス・鉄道・自動車など複数の移動手段を瞬時に組み合わせ、目的地まで効率的かつ安く利用できるようになります。
MaaSが社会で活発化することにより、交通難民に対する新しい形での移動手段の提供や、効率的な運行による道路渋滞の改善などが見込めます。
MaaSという概念が世界中に浸透すれば、自動車業界はこれまでの「車を売って終わり」というスタンスから、自動車を使ってサービスを提供するスタンスにシフトすることが求められるでしょう。
参照:
・「【自動車業界のDX事例】社会に大きな影響を与える4要素”CASE”」DXportal
・「自動車業界とDX(CASEとは、MaaSとは)、海外(米国・中国・インド・ASEAN)の動向」プルーヴ株式会社
・「トヨタのコネクティッドサービス | T-Connectのサービス」トヨタ自動車
・「自動運転はどこまで進んでいますか?」 JAF
・「自動運転”レベル4″解禁へ 政府、法改正案を閣議決定」日本経済新聞
・「自動運転レベル4、ドイツが”世界初”公道解禁へ」自動運転ラボ
・「自動車:日本版ライドシェア(自家用車活用事業)関係情報 」国土交通省
・「議長国主導の脱ガソリン車、宣言に23カ国 実効性不透明」日本経済新聞
・「リーフ [ LEAF ] | 航続距離・充電 | 航続距離・バッテリー」日産自動車
・「電気自動車(EV)とは?メリット・デメリットもあわせて解説します」エネチェンジ
・「圧巻の走りを秘めたホンキのEV テスラ”モデル3 パフォーマンス”」BRUDER
海外の自動車業界DX事例1:VR技術を用いた体験スペース

ドイツの高級車メーカーの一つ・Audiは、「Audi City」というバーチャルショールームを展開しています。
バーチャルショールームでは、ユーザーの希望に合ったオプション等を装着した状態の「自分だけの一台」を、VRゴーグルで確認できます。
バーチャルショールームの採用により、従来のショールームと比較して売上高が60%増加したケースもあることから、将来的により多くの店舗で採用される可能性があります。
参照:
・「”4つの成功要素”を網羅した、海外におけるDX先行事例③」Cogent Labs
・「DXの欧州事例1: Audiのショールーム改革(Audi City)」ドイツビジネスコンサルティング
・「バーチャルショールーム」
海外の自動車業界DX事例2:自動車がWebサイトで購入できる

一般的に、自動車を購入する場合は店舗に足を運び、担当者と相談した上で購入を決定します。
しかし、テスラではWebサイトから自動車を直接購入できる仕組みができており、ディーラー等で不親切な担当者から売り込みをかけられるリスクが減ります。
サイト内では、ボディカラー・ホイール・シートレイアウトなどを自分で選択できるため、担当者の意見に惑わされることなく大きな買い物ができます。
参照:
・「テスラの衝撃―EVの常識を覆した戦略 –」TECHBLITZ
・「Model X 」 Teslaジャパン
海外の自動車業界DX事例3:移動サービスの一元化

MaaSの分野において一歩先を行っている国の一つが台湾です。
台湾の高雄市ではスマートフォンアプリ「Men-GO」とICカード「iPass」による月額定額制でのサービスを提供しています。
電車やLRT、バスといった公共交通機関に加え、タクシーやレンタルサイクル、フェリー、自転車シェアリングと市内で利用できる、さまざまな交通手段と連携が取れており、ルート検索も可能です。
「Men-GO」の導入によって、Men-GOユーザーの交通費削減や交通事業者の収益拡大、ユーザーの交通行動の把握という成果が出ました。
参照:
・「モビリティクラウドを活用した シームレスな移動サービス(MaaS)の 動向・効果等に関する調査研究」国土交通政策研究所
・「MaaSを導入している台湾の現状とは?海外の事例を知っておこう」Digital Shift Times
自動車業界DXの海外事例課題

自動車業界における日本の技術力はトップクラスであり、海外でも日本車は高い人気を誇ります。
一方で、その自動車を「どのように活用するか」を考えるのは、日本の自動車業界にとっては難題の一つです。
もともと、日本の自動車業界が成長したのは、欧米諸国のキャッチアップからの大量生産、既存の車両の改善・改良を重ねる中での進化によるものでした。
しかし、物事が多様化する中で自動車を取り巻く環境も変わり、ただ自動車という商品を作る・売るだけでは売上も頭打ちになるものと推察され、DXへの発展も望めません。
ユーザーの自動車購入に頼らず、自動車がユーザーに提供できる価値を増やして収益を得ることが、これからの日本の自動車業界には求められます。
個人の中古車販売店などの零細事業者であっても、チャンス次第では在庫を貴重な収入源にすることができるかもしれません。
その点において、今回ご紹介した事例やCASE・MaaSという概念を正しく理解することは、今後のDXの方向性を決める指針となるでしょう。
自動車業界DXの海外事例まとめ

自動車業界におけるDXは、他の業界も巻き込む大きな動きになって進化することが予想されます。
また、環境保全や交通手段の多様化にともない、世界が求める自動車のイメージも変化しています。
自動車を単なる移動手段としてとらえるのではなく、どのような付加価値をつけられるのかを考えることで、新しいビジネスチャンスが生まれるかもしれません。
日本でも推進が必要とされるDX分野で、ぜひあなたの経験を活かしてみませんか?
・会社員で副業を探している
・週に1、2日だけ稼働できる案件を知りたい
・DXコンサルタントに興味がある
・まだ仕事を受けることは考えていないけど、どんな仕事があるのか知りたい
・働く場所にとらわれずリモート案件を探したい
そんなデジタル人材の活躍を「コンタクトアース」は応援しています!
活躍の場が広がる無料登録に必要なのは、名前、メールアドレス、電話番号だけなので簡単にできます。
あなたも「コンタクトアース・マッチング」に登録してみませんか?
DXに関わるコンサルタントやエンジニアの方へ無料登録はこちら

✔全案件が完全リモート/高単価の案件多数 100万円以上の案件が80%以上
✔週1回~フルタイムまで自分で稼働日数を選べます。
✔働きたい時にすぐ働けて、最短2日で仕事に入れます。
✔本サービスの仕事はDX案件に特化