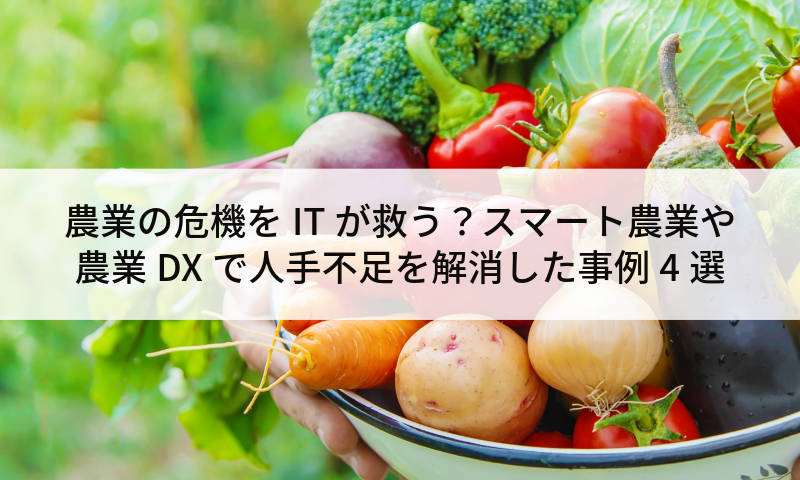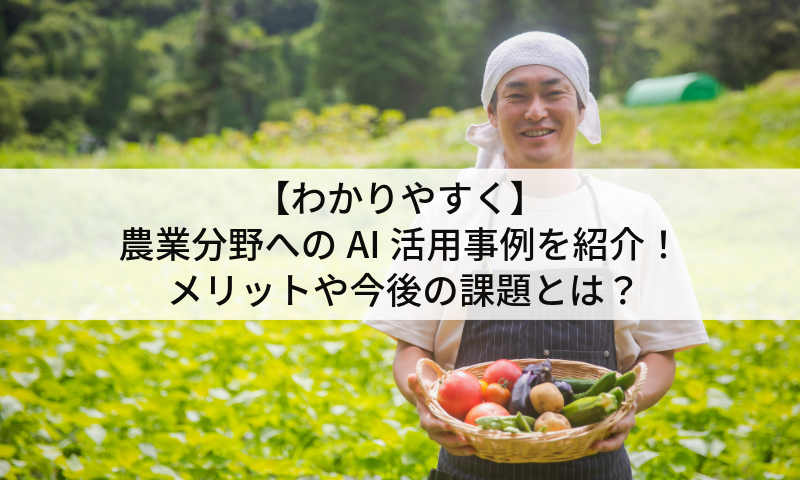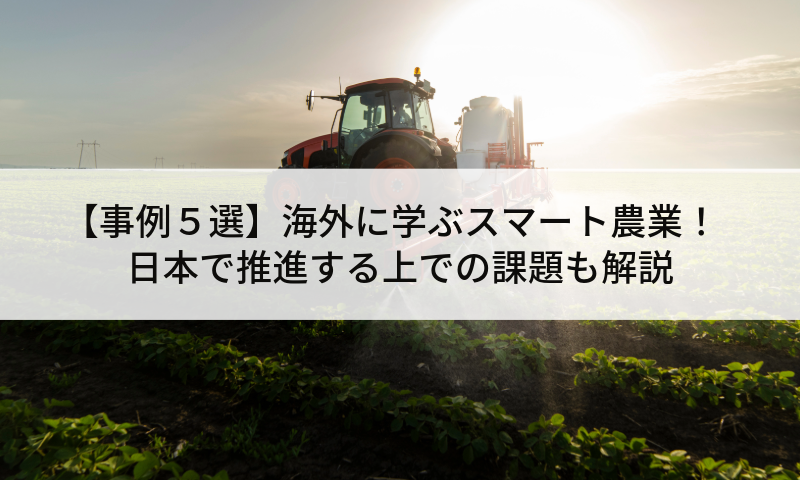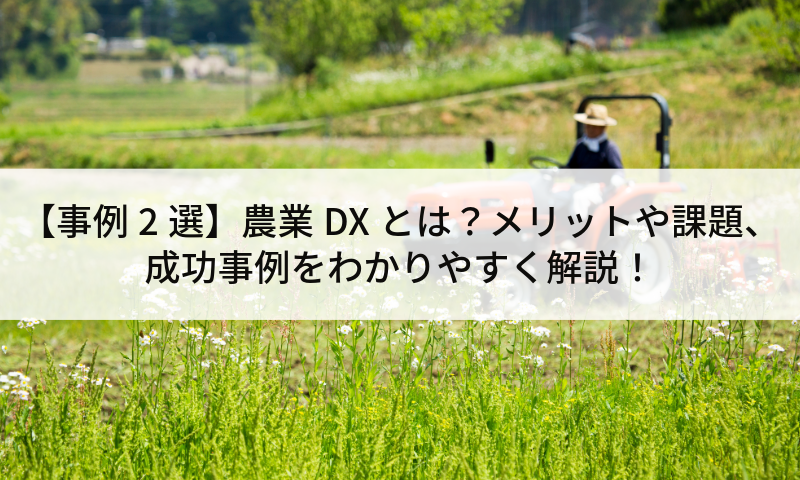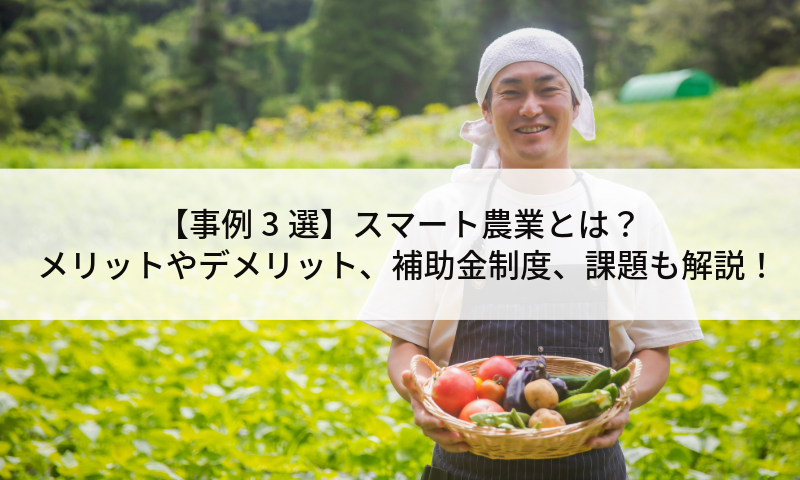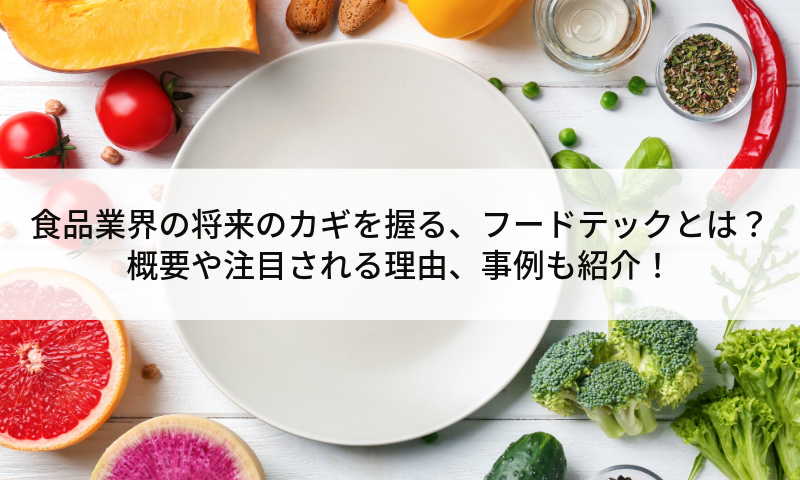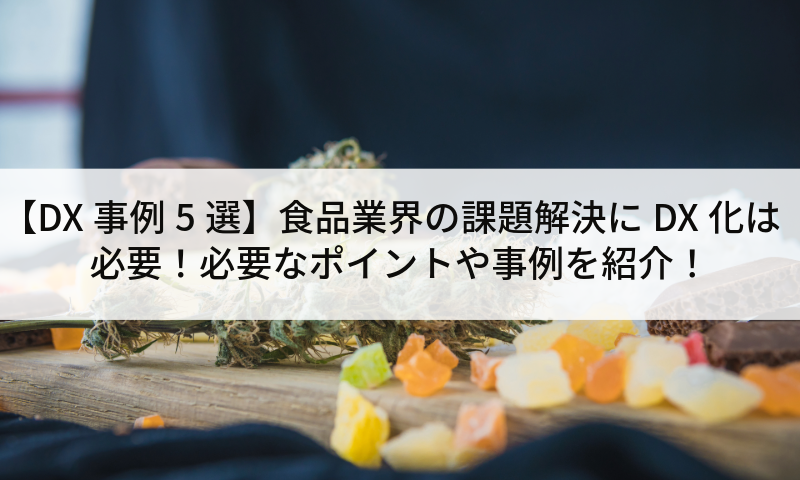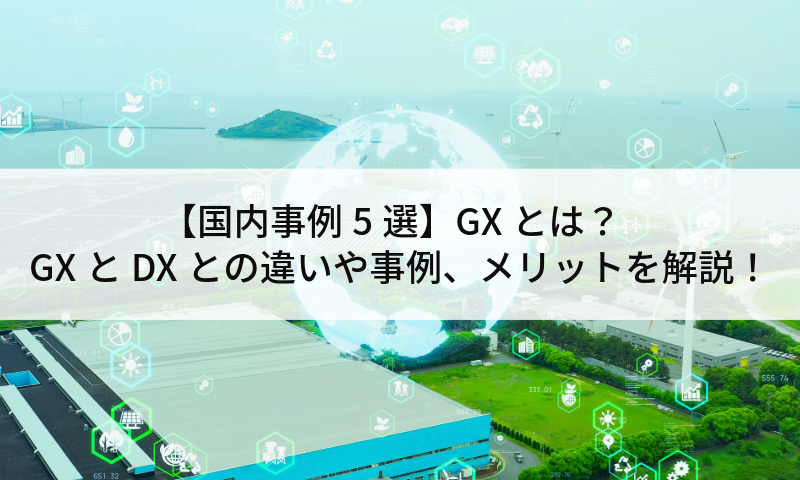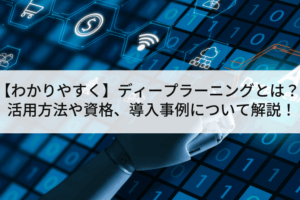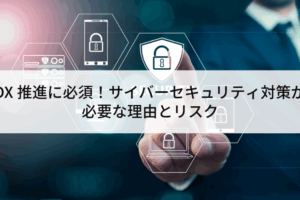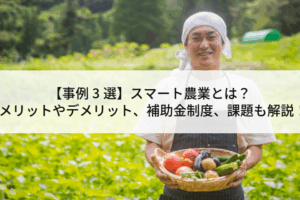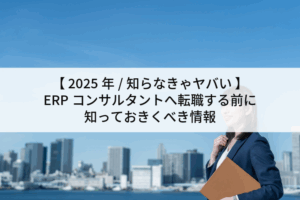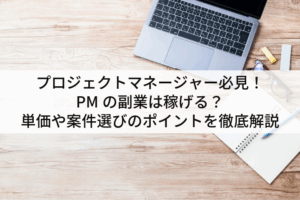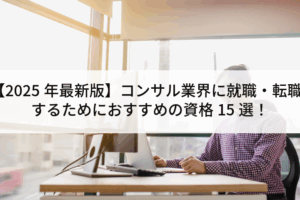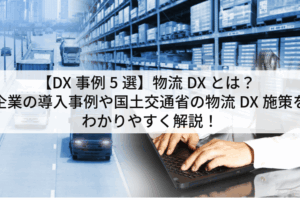水産庁が次世代の水産業として推進する「スマート漁業」。
ICTやIoTなどの最新技術を駆使することで、水揚げ量の安定化や若手への事業継承など、現代の漁業が抱えている問題解決を目指す取り組みです。
例えば、AIが漁場を予測して養殖で魚の摂餌状況を自動で管理したり、漁師の勘を見える化したりする仕組みが実用化されています。
この記事では、企業での実際の導入例や、もたらす効果と解決すべき問題について解説していきます。

目次
AIを活用したスマート漁業の事例を紹介
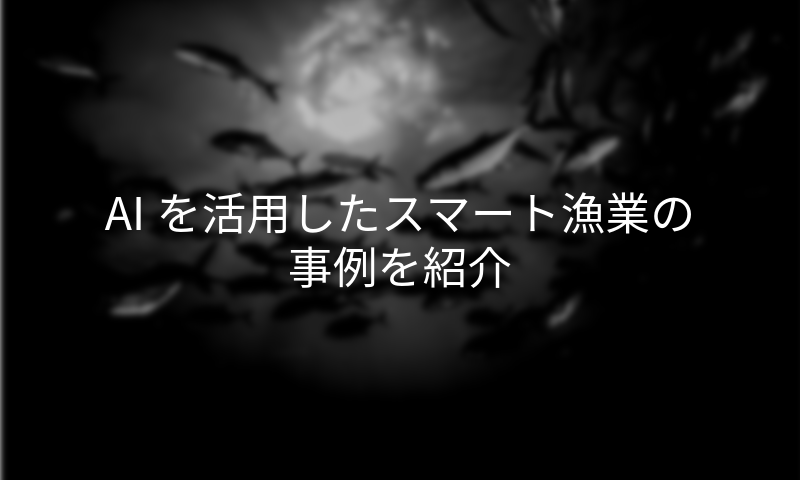
近年は水産分野においても、資源の持続的利用と水産業の成長産業化の両立を目指し、AIなどのIT技術の積極的な採用が広がっています。
ここでは、具体的なプロジェクトを3つ紹介します。
● KDDI|海洋ビッグデータを活用したスマート漁業
● オーシャンソリューションテクノロジー|衛星データと連携した漁業支援システム
くら寿司|AIを活用したスマート養殖
くら寿司は2021年より、子会社「KURAおさかなファーム」を通じて、スマート養殖に取り組んでいます。
AIとICT技術を用いて養殖環境を数値化し、データを収集することで、給餌計画や生産管理の効率化を実現しました。
例えばAIを用いた給餌システムでは、画像解析により魚の食欲を判定し、最適なタイミングで必要に応じた量の餌を自動的に供給します。
その結果、エサ使用量を10%削減できただけでなく、燃料費や労働コストの軽減も実現しました。
さらに、スマートフォンを使った遠隔管理で現場作業の負担を大幅に軽減し、労働環境の改善にもつながっています。
そして、育てた魚をくら寿司が全量買い取り販売する仕組みを導入し、生産者の収入安定と高品質な寿司の安定供給を両立。
AI桜鯛にハマチやスマガツオ、マグロへと対象を拡大し、持続可能な水産業モデルとして発展を続けています。
このように、くら寿司はデジタルを駆使したスマート養殖によって、漁業現場の改善と水産業全体の持続的成長を両立させています。
参照:
・「くら寿司の新戦略!持続可能な漁業の実現に向けた『スマート養殖』 ~AIなどを駆使した”スマート養殖”で人手不足や労働環境を改善!大手外食チェーン初!AI桜鯛”も新登場!~」くら寿司
・「漁業におけるAIの活用事例9選!漁獲量UPや流通・品質管理改善など」ニューラルオプト
KDDI|海洋ビッグデータを活用したスマート漁業
KDDIは、IoTやビッグデータを用いたスマート漁業に取り組んでいます。
漁場の気温・水温・潮流・塩分濃度などをIoTセンサーで計測し、auの通信ネットワークを通じてデータを収集しています。
このデータと漁師が入力する水揚げ量の記録と組み合わせ、勘や経験を客観的に「見える化」し、漁業の計画をより効率化しました。
例えば宮城県東松島市のサケ漁では、2種類のスマートブイを用いて海洋環境と水揚げ量の関係を分析し、出航計画の精度向上を目指しています。
また、京都府舞鶴市の「丹後とり貝」養殖事業では、昇降機付きのIoTセンサーが水深ごとの水質データを収集してクラウド上で解析。
生育環境を数値化することで、良質なとり貝の安定的な育成や、異常発生時の迅速な原因究明に役立てています。
これらの取り組みは、水揚げ量の安定化や若手漁師への技術の伝承につながり、地域漁業の持続的発展を後押ししています。
通信技術を基盤とするKDDIが進めるスマート漁業は、日本の漁業を効率化し、持続可能な未来へとつなげる新しいモデルといえるでしょう。
参照:
・「勘や経験だけに頼らない! 海洋ビッグデータを活用した『スマート漁業』始まる」KDDI トビラ
・「KDDIのつなぐストーリー vol.2|“願い”をもって漁業の現場でデジタルと人をつなげる」ELEMINIST(エレミニスト)
オーシャンソリューションテクノロジー|衛星データと連携した漁業支援システム
オーシャンソリューションテクノロジー株式会社(OST)は、日本の準天頂衛星システム「みちびき」とAIを組み合わせ、操業データの自動化と効率化を進めています。
OSTがブロックチェーンを活用して開発した漁業支援システムが「トリトンの矛」です。
漁船に搭載したIoT機器から高精度な位置情報と航跡データを取得し、AIが解析することで操業日誌を自動生成できます。
従来は手作業だった記録が効率化され、漁師の勘や経験もデータとして残すことができるため、若手漁師へのスムーズな技術の伝承が可能になりました。
さらに操業場所や時間などの情報は漁獲物のトレーサビリティを実現し、消費者への水産物の安心・安全を担保すると同時に、付加価値の向上にもつながります。
また「みちびき」の災害・危機管理通報を受信できる仕組みも導入し、電波の届かない洋上でも災害情報を受信することで、漁業者の安全確保にも大きく貢献しています。
OSTの挑戦は漁業者の負担軽減だけでなく、消費者の安心や社会全体の持続可能性にもつながる取り組みといえるでしょう。
参照:
・「オーシャンソリューションテクノロジー:トリトンの矛」
・「続・未来の漁業革命!準天頂衛星”みちびき”とAIの進化がもたらす自動漁業操業情報の新展開 」PR TIMES
・「[実証2023-1] OST:みちびきを利用したAIによる漁業操業情報の自動作成|利活用事例集」みちびき(準天頂衛星システム:QZSS)公式サイト
スマート漁業を導入するメリット
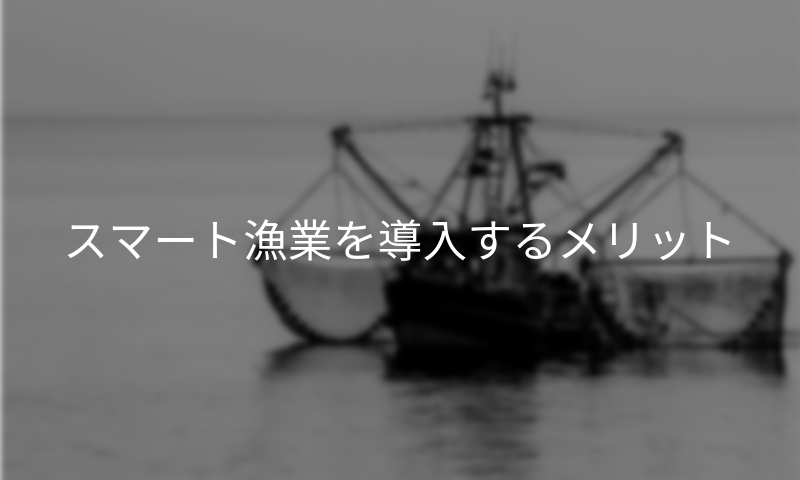
現代の漁業では、資源の減少や就業者の高齢化が、喫緊の問題として挙げられます。
IoTやデータ解析などの先端技術を通じて、問題解決につながる以下のメリットが得られます。
● 事業継承がスムーズになる
生産性が向上する
スマート漁業の大きな利点は、生産性を高められる点です。
従来の漁業は天候や潮流に左右されるため安定した操業が難しいことに加えて、情報の共有方法が無線や紙媒体が中心だったため、効率化に限界がありました。
しかしAIやIoTを導入すれば、衛星情報やAIによる漁場予測で無駄な航海を減らし、燃料費や作業時間を削減可能です。
さらに、漁業者と市場がリアルタイムで情報を共有することで、効率的な操業や流通につながります。
このように先端技術によって、限られた資源や人員でも成果を最大化し、水産業界全体のパフォーマンスの底上げが可能です。
参照:
・「スマート漁業とは?水産業でのAI・IoT 活用のメリットや事例・課題を解説」AIsmiley
・「スマート漁業とは?AIを活用するメリットや実際の企業事例を解説」オルツ
事業継承がスムーズになる
スマート漁業は、事業継承をスムーズに進めるためにも有効です。
これまでの漁業は漁のノウハウが属人化しており、若手への伝承が難しいとされてきました。
AIによって情報の可視化を進めれば、漁場の見極め方や作業の工夫が数値や映像として蓄積され、学びやすい形に整理することが可能です。
例えば、漁獲実績と海況データの関係を解析して見える化すれば、経験の浅い漁業者でも客観的な情報をもとに熟練者に近い判断が可能になるでしょう。
さらにシミュレーションやVR訓練を組み合わせれば、危険を伴わずに操業の流れを体験でき、実践力を効率的に磨けます。
スマート漁業の導入は後継者不足の解消につながり、世代交代を支えながら地域の漁業を未来へと引き継いでいく基盤となります。
参照:
・「スマート漁業とは?水産業でのAI・IoT 活用のメリットや事例・課題を解説」AIsmiley
・「スマート漁業とは?AIを活用するメリットや実際の企業事例を解説」オルツ
スマート漁業を導入するデメリット
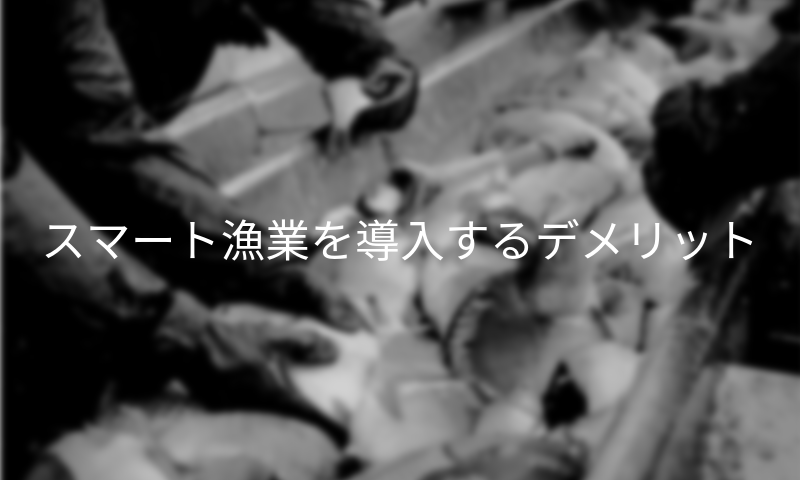
メリットを得られる一方で、スマート漁業に取り組むためには、解決すべき問題も存在します。
水産業におけるスマート化のデメリットとして、以下の2点を解決策と併せて解説します。
● 手厚いサポートが必要になる
初期費用がかかる
スマート漁業の大きな課題の一つは、導入時に発生する初期費用です。
IoTセンサーや通信機器、データ分析システムといった機材は高額なため、導入時には重い負担として水産業者にのしかかります。
例えば、海洋データを測定するICTブイや養殖で使用する自動監視システムには、数百万円規模の投資が必要になる場合もあります。
こうした高コストは導入のハードルを上げ、漁業のデジタル化をためらう要因となりやすいでしょう。
しかし、水産庁の事業では、機器導入に対する補助金制度が設けられており、条件によっては費用の1/2から2/3まで支援を受けられます。
この制度を活用すれば初期費用の負担を抑えつつ、スマート漁業を取り入れられます。
参照:
・「スマート漁業とは?水産業でのAI・IoT 活用のメリットや事例・課題を解説」AIsmiley
・「スマート漁業とは?AIを活用するメリットや実際の企業事例を解説」オルツ
・「スマート水産業普及推進事業について」水産庁ホームページ
手厚いサポートが必要になる
スマート漁業を現場で定着させるためには、手厚いサポートが求められます。
漁業の現場ではITに関する知識が不足するケースもあり、新しい機器やシステムの操作に戸惑う場面も少なくありません。
例えば、自動給餌機の調整やAI解析は、初めて扱う人にとっては難しく感じられるかもしれません。
こうした課題に対し、水産庁は現場の漁師を支える仕組みを整えています。
事業実施機関が推薦し、専門的な講習を受けた「伴走者」が、導入計画の立案から効果測定まで一貫して支援する体制です。
この伴走者制度により、導入後も安心して機器を運用できる環境が整い、現場の負担を減らしながらスマート漁業の定着が促進されます。
参照:
・「スマート漁業とは?水産業でのAI・IoT 活用のメリットや事例・課題を解説」AIsmiley
・「スマート漁業とは?AIを活用するメリットや実際の企業事例を解説」オルツ
・「スマート水産業普及推進事業について」水産庁ホームページ
まとめ
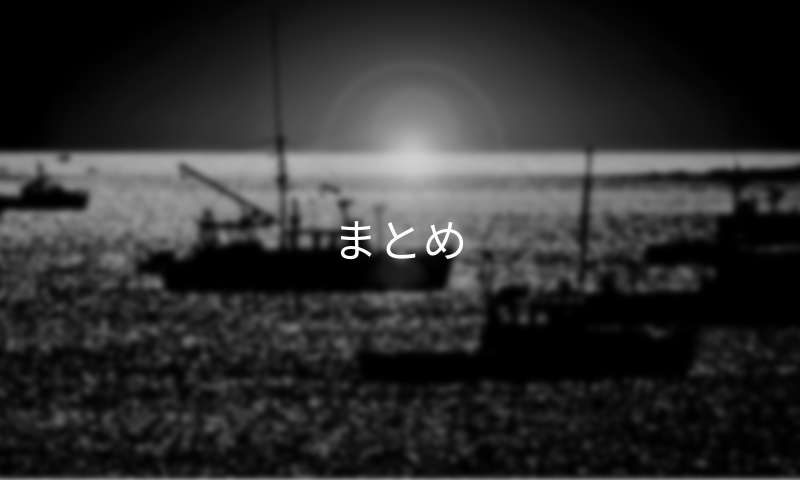
この記事では、スマート漁業を取り入れた企業の実践例や、メリット・デメリットについて解説しました。
水揚げ量が安定しない、担い手が不足していくなど課題を抱えている水産分野では、その解決策としてスマート漁業が注目されています。
従来の経験や勘に頼る方法から、AIやデータを有効活用する方法に移行することで、生産効率が高まり事業の引き継ぎがスムーズになります。
AIを通じたスマート漁業は、効率的で持続可能な業態へと水産分野を進化させてくれる存在です。
● まだ仕事を受けることは考えていないけど、どんな案件があるのか知りたい
● 働く場所にとらわれずリモートでできる案件を探したい
フリーランス向けのフルリモート案件をお探しの方へ

✔高単価案件多数
150万円以上の案件が80%以上、200万円以上も!
✔フルリモート案件多数
リモートで完結するDX・戦略案件が見つかる
✔上場企業や優良企業から直接スカウトが届く
簡単なプロフを見てみる