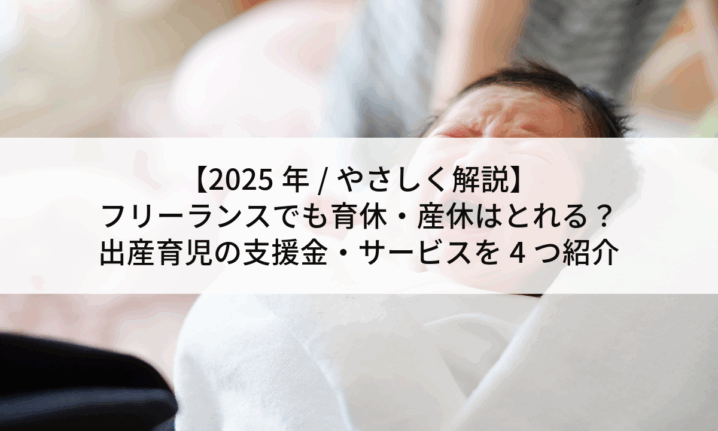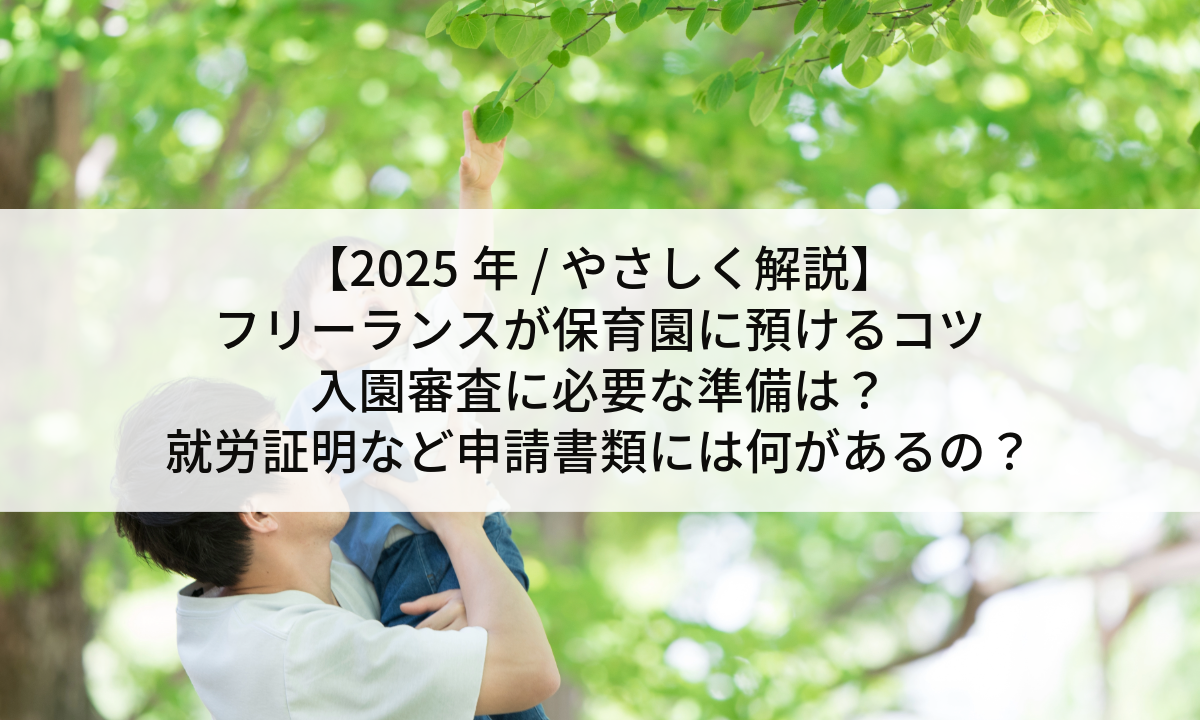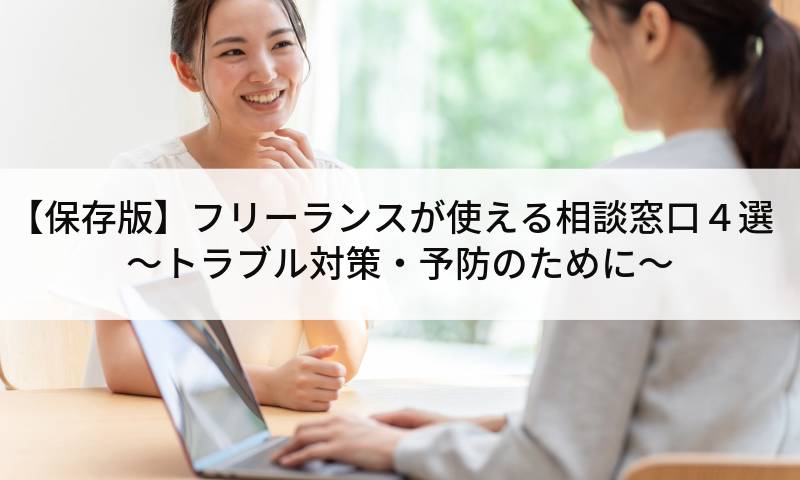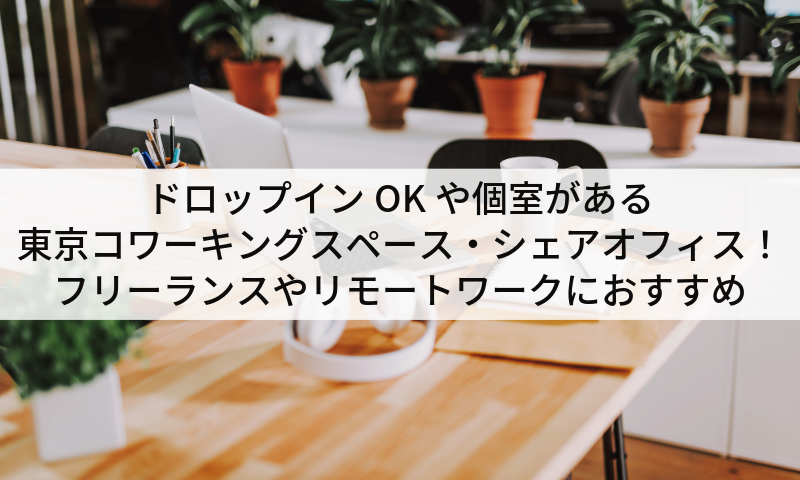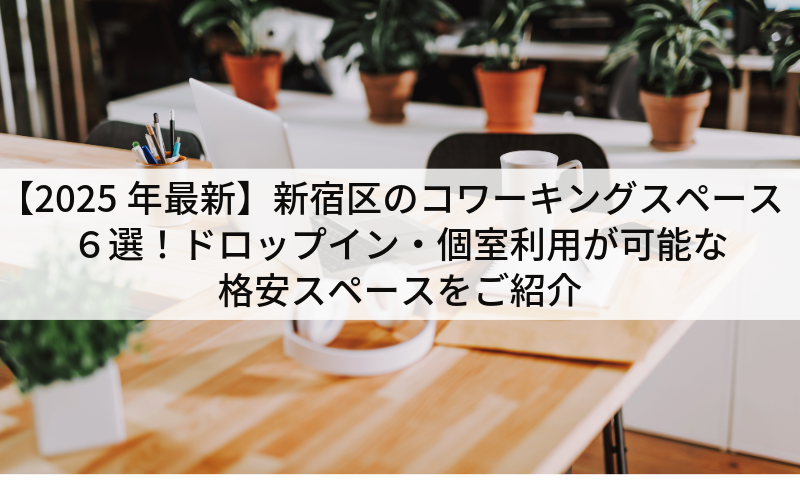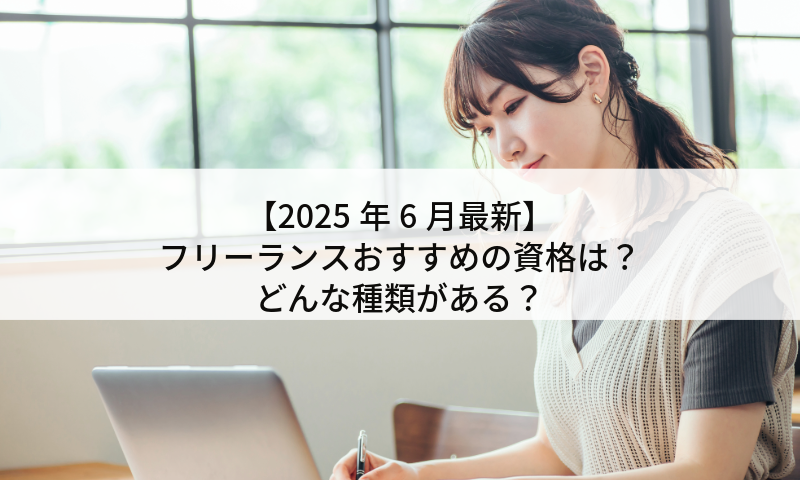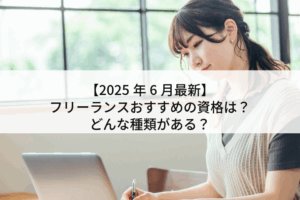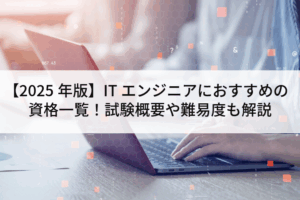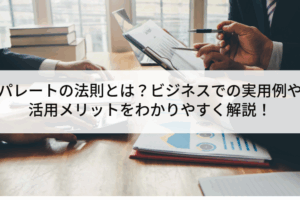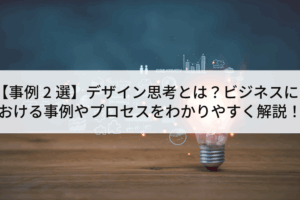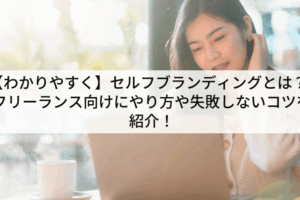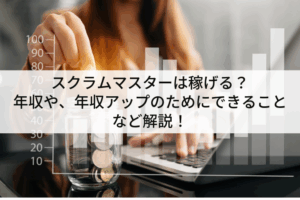こんにちは。当メディアを運営するストラテジーテックコンサルティング編集部です。
働き方改革やリモートワークの推奨により、フリーランスを目指す方が増えていますよね。
フリーランスと聞けば「自由な働き方」をイメージされる方が多いと思いますが、社会的なデメリットも多く抱えています。
その一つに、出産・育児に関する支援があります。
そこで本記事では、フリーランスにまつわる育休・産休に関する情報とフリーランスでも受けられる支援制度についてまとめました。
Contact EARTH matchingでは、フリーランスエンジニアを募集する高単価案件が多く掲載されています。
日本の有名企業や大企業、官公庁におけるDX化を推進する案件も扱っていますので、無料エキスパート登録を行い案件を探してみてください。

目次
フリーランスへの出産育児の支援制度は?

働き方の多様化が進む中、フリーランスという働き方も少しずつ広まりつつあります。
しかし、それに伴う支援制度の整備や情報の普及は、まだ十分に追いついていないのが現状です。
例えば「雇用関係によらない働き方と子育て研究会」が実施した調査によると、出産後も働き続けた女性フリーランス288人のうち、約45%が産後1カ月以内に仕事を再開していたことがわかりました。
こうした実態からも、出産や育児に関する支援について「よく分からず不安」と感じている方は少なくないのではないでしょうか。
出産や育児は、多くの人が人生の中で直面する可能性のある出来事です。
特に女性の場合、妊娠中や産後の体調によっては、働きたくても働けない状況になることもあるでしょう。
そのようなとき、会社員と同じように、フリーランスでも産休や育休などの支援制度を利用できるかどうかは、非常に重要なポイントになります。
参照:「”産後1カ月中に仕事再開”フリーランス女性らの半数」朝日新聞
フリーランスでは育休産休は取れない
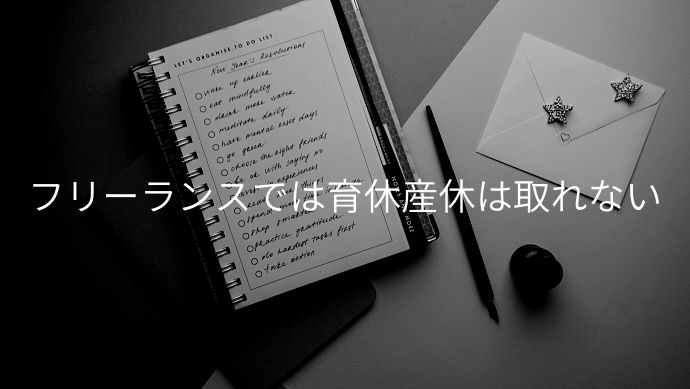
結論から言いますと、残念ながらフリーランスの方は育休産休などの制度を利用することはできません。
これらの制度は「雇用者」を対象としたものだからです。
育休・産休制度は、会社に雇われて働くサラリーマンなどの従業員を保護するために設けられた制度であり、自ら事業を営むフリーランスや自営業者は制度の対象外となっています。
そのため、出産などで働けなくなる可能性がある場合には、自身で受注する仕事の件数やスケジュールを調整しておく必要があります。
特に継続的な契約を結んでいる取引先がある場合は、早めに事情を伝えて相談しておくと安心です。
育児休業給付金ももらえない
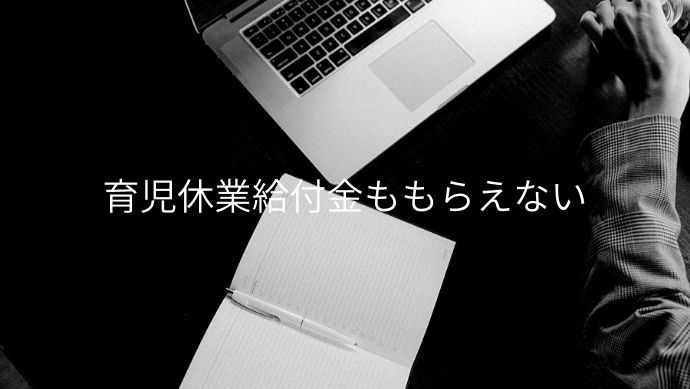
子育てで働けない時、やはり気になってしまうのがお金のこと。
会社員などの雇用されている立場であれば、「育児休業給付金」という制度を利用できる場合があります。
これは育児休業中の収入を一定程度保証するもので、雇用保険に加入している人が対象となります。
一方、フリーランスの場合は雇用保険に加入していないため、この育児休業給付金を受け取ることはできません。
フリーランスは働き方の自由度が高い反面、こうした「いざというときの保障がない」というデメリットと向き合う必要があります。
だからこそ、将来を見据えた備えや制度の理解がより一層重要になります。
フリーランスでも受けられる育休産休の支援4選

前述のとおり、フリーランスは「雇用者」を対象とした育休・産休制度の恩恵を受けることはできません。
しかし、フリーランスであっても利用できる出産・育児に関する支援制度は存在します。
制度の内容を知っておくことで、出産や育児の不安を少しでも軽減することができるはずです。
妊婦検診費用助成
妊娠した場合、定期的に月に1~2回は検診に行く必要があります。
しかし、この検診費用、個人で負担するとなるとかなりの金額がかかってしまいます。
「妊婦検診費用助成」とは、その検診費用を自治体が補助してくれる制度。
妊娠していれば誰でも対象に含まれるので、フリーランスの女性でも利用できます。
役所で、母子手帳と補助券を一緒に渡してくれると思いますので、確認してみましょう。
また、自治体や収入によっては妊娠中の診察のときに受けられる他の補助についても教えてくれる場合があります。
母子手帳を受け取る際に役所の方に聞いてみてください。
出産育児一時金
出産時にかかる際のお金は(病院の設備や母子の状態にもよりますが)40~60万ほどと言われています。
一般家庭にとっては軽く見ていい金額ではありませんよね。
ここで活用したいのが「出産育児一時金」。
自治体から42万円分の補助を受けることができる制度です。
国民健康保険に入っていればフリーランスの方でも受けられます。
基本的に出産した病院側が申請してくれますが、そうではない場合は役場で申請することも可能です。
国民年金保険料の免除
以前までは、会社員の方に限り「産前産後休業保険料免除制度」によって健康保険、厚生年金保険の納付が免除されていました。
しかし2019年から、フリーランスの方が加入する国民年金も免除制度の対象に含まれるようになりました。
出産産後の4か月分が免除になります。
役場の国民年金担当窓口に届書を提出するだけでよく、出産予定日の6か月前から出産後の期間で提出することができます。
参照:
・「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」日本年金機構
・「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」日本年金機構
児童手当
産まれてから義務教育である中学校卒業まで、一定金額支給される「児童手当」はフリーランスの方でも受け取ることができます。
3歳未満の子どもがいる場合は月額15,000円、3歳以上から高校生年代までの子どもがいる場合は月額10,000円が支給されます。
支給は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に行われ、それぞれの前月分まで、つまり2か月分がまとめて振り込まれます。
児童手当は申請書を出した次の月から支給になります。
ですので、出産したらすぐに申請を自治体に出してください。
産まれた日が月末でも、15日以内に申請すれば申請した月から支給してくれるので忘れないようにしましょう。
フリーランスの出産育児を乗り越える方法3選
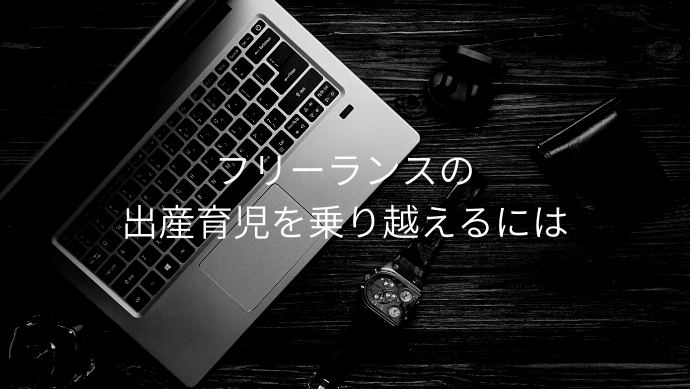
自分の力で乗り越えなければいけないフリーランスの出産育児。
ストレスなくに進めるにはどうしたらいいのでしょうか。
出産育児をスムーズに乗り越えるべく、押さえておきたいポイントをご紹介します。
クライアントとの連絡は密に
自分で仕事を探して契約を取るフリーランスにとって人脈はかけがえのないもの。
産後落ち着いた後にもクライアントとのいい関係を続けたいのであれば、出産予定の半年ぐらい前からクライアントには伝えておいたほうがいいでしょう。
その後仕事を再開するめどが立った際にもきちんと連絡を入れておいてください。
きちんとした信頼関係を築いておくことで、スムーズに仕事を始められます。
産まれる前の新規の仕事は慎重に
「産後はすぐ働けないから少しでも余裕がある今のうちに」と、焦って新規の仕事を取ろうとする人も多いかもしれません。
しかし、出産ぎりぎりまで働くようなペース配分にはしないようにしましょう。
出産育児は何があるかわからないことばかりです。妊娠中に何かあって入院なんて話も珍しいことではありません。
お金が足りなくなるかもと不安になる気持ちもわかります。
しかし、無理なペースで仕事を続け、結果クライアントとの関係にひびが入ってしまった…となる方が大きな損害でしょう。
産後の子供預け先は最優先確保
お子さんが産まれたあと何か月かは家で育てるとして、その後、働く際に子供を預かってもらえる先を確保する必要があります。
産まれた後探せばいいとゆっくり考えている方もいるかもしれませんが、フリーランスの場合はそれでは甘い可能性が高いので、気をつけてください。
フリーランスの場合は、通常の会社員よりも保育所の優先度が低く見られている場合が多いのです。
自治体によっては、フリーランスが認可保育所の利用を断られるというケースも報告されています。
激戦区の保育園探しを乗り越えるためには、生まれる前から自治体に相談しておくことが好手です。
認可外保育施設や他のサービスなども視野に入れながら、時間をかけて探しましょう。
フリーランスの保育園入園に必要なテクニックや書類は以下の記事で詳しく解説していますので、併せて参考にしてみてください。
フリーランスでもきちんと準備して子育てと仕事の両立を
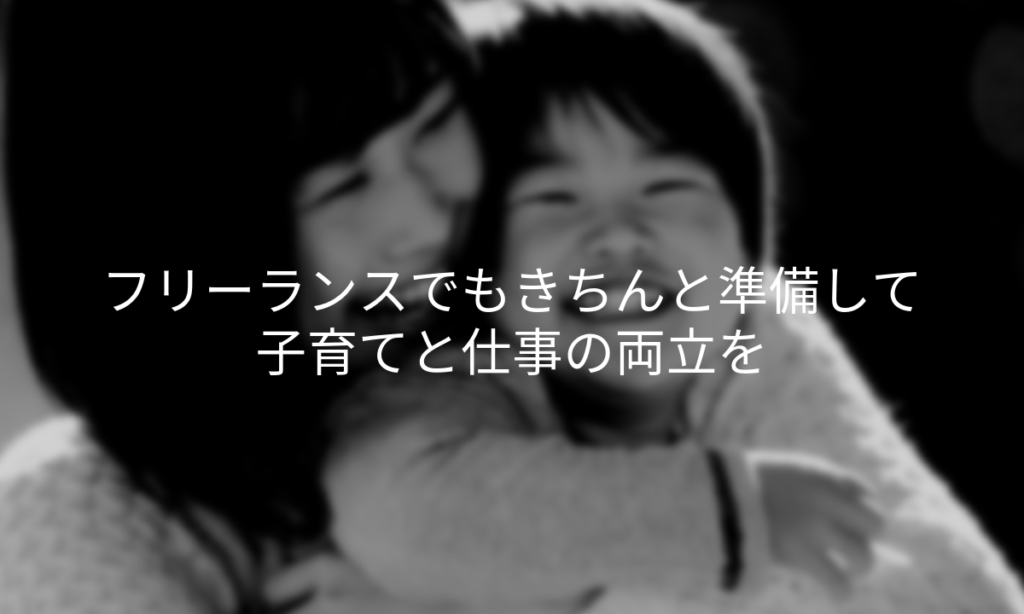
ここまでフリーランスの方向けに、出産育児に関する制度を中心にご紹介してきましたが、いかがでしょうか。
フリーランスは柔軟に仕事ができるというメリットがある反面、大変なときは自分で解決しなければならないというデメリットも存在します。
実際、出産育児に関する補助も会社員に比べると少ないのです。
しかし、きちんと前もって準備をしておけば、フリーランスでも子育てと仕事を両立させることは可能です。
この記事を参考にし、自治体などともよく相談しながら、安定した子育てライフを送れるように頑張ってください。
最後に、フリーランスの方に弊社のコンタクトアースマッチングをおすすめいたします。
まずはかんたん10秒の無料会員登録を行って、最新の高単価案件を覗いてみてください。
フリーランスの方へ無料登録はこちら

✔全案件が完全リモート/高単価の案件多数 100万円以上の案件が80%以上
✔週1回~フルタイムまで自分で稼働日数を選べます。
✔働きたい時にすぐ働けて、最短2日で仕事に入れます。
✔本サービスの仕事はDX案件に特化