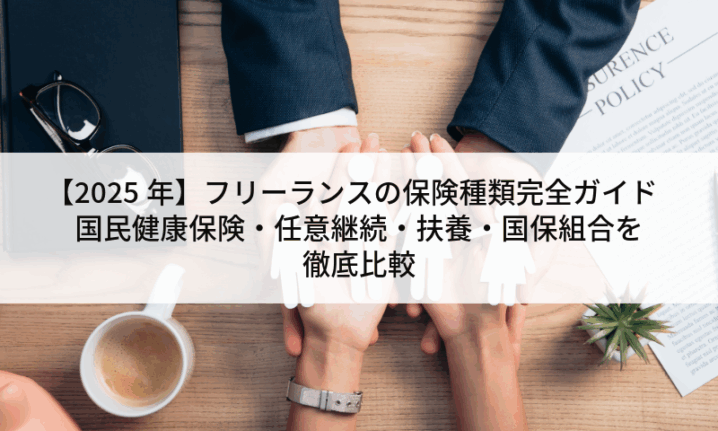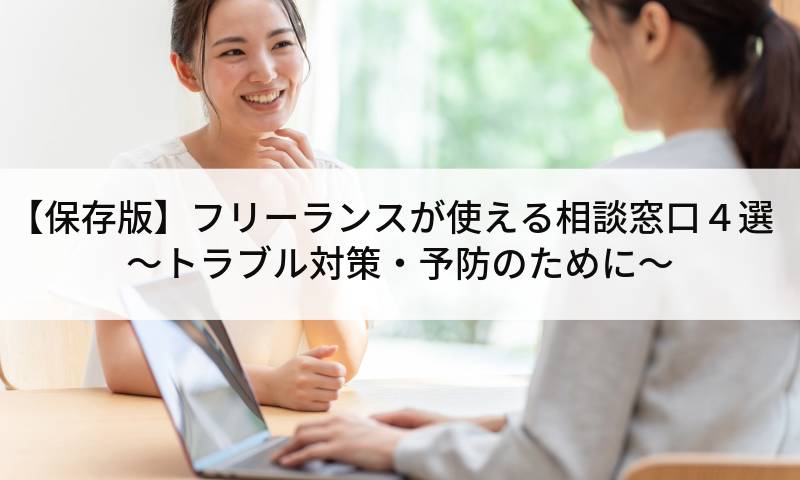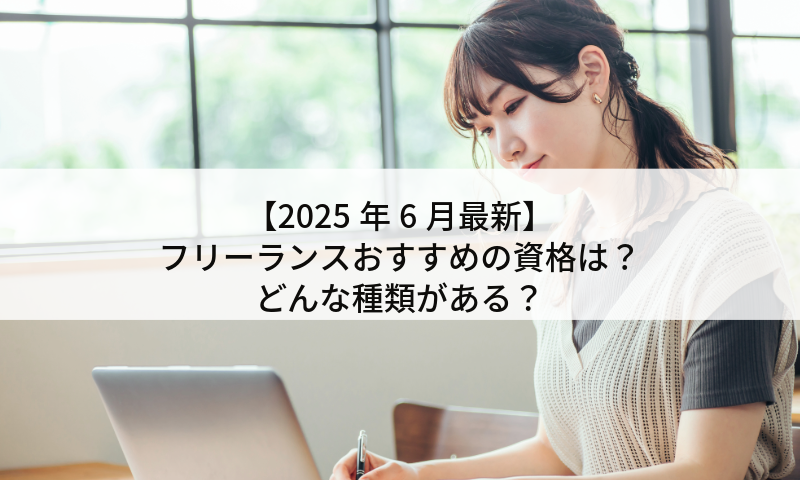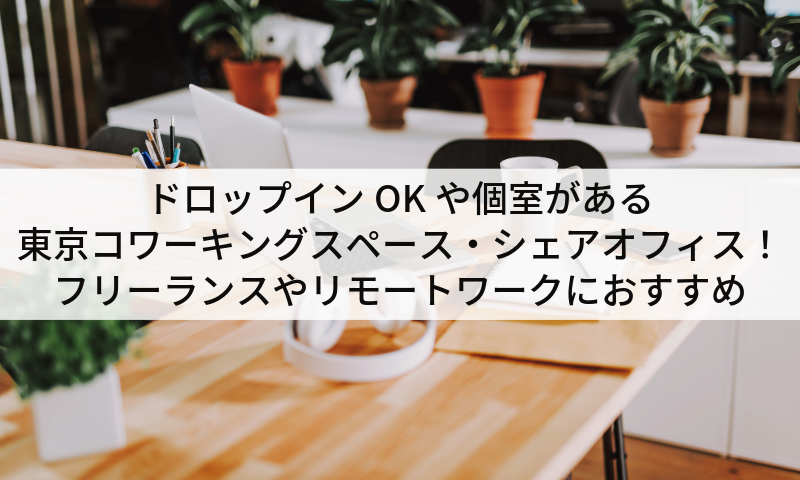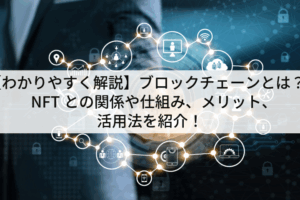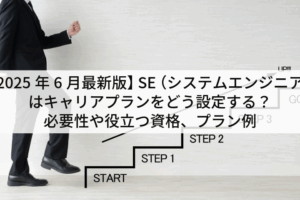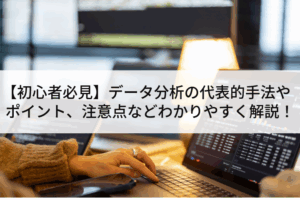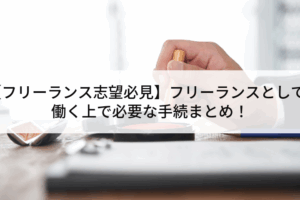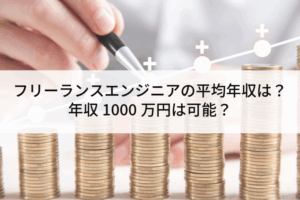こんにちは。当メディアを運営するストラテジーテックコンサルティング編集部です。
フリーランスとして働かれている方も多くいる、現代。
内閣府政策統括官が2019年7月発表した資料では、日本のフリーランスの人口は、306~341万人と言われています。
また、ランサーズ株式会社が発表した「フリーランス実態調査 2024年」ではフリーランス人口は約1,300万人にも達し、経済規模は20兆円を超えるといいます。
今後もより一層、フリーランス人口は増えて行くことが考えられます。
本記事では現在、フリーランスとして働かれている方やこれからフリーランスとして働きたいと考えられている方のために、今日のフリーランスの保険事情について解説しました。

目次
フリーランスが加入できる保険の種類4つ
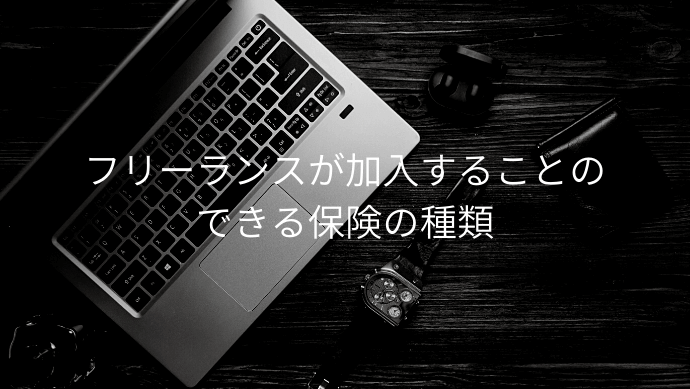
フリーランスは、4つの保険に加入することができます。それぞれの保険について確認していきましょう。
1.国民健康保険
国民健康保険は、自営業や会社に勤めていない方などが対象となる保険です。
また、保険の運営は各自治体によって行われているため、保険費用は各自治体によって異なることも特徴の1つです。
保険料の算定基準は、前年度の所得収入と家族の人数や年齢に起因します。
前職で高額な収入を得ていた方には十分注意が必要です。
保険加入に際しては、自動で加入されるわけではないので、加入が必要であれば、退職してから14日以内に市役所の窓口へ行き、手続きを行わなければなりません。
各自治体によって必要書類は変わってくる場合がありますが、下記に東京都港区の場合に必要書類を記載いたしますので、参考までにご準備ください。
前職が会社員だった場合、以前所属していた勤務先の健康保険を継続して加入することも可能です。 しかし、継続するにあたり、デメリットも存在します。 それは保険料の全額負担と加入期間の制限です。 会社員の頃は健康保険の保険料の半分を会社が支払い加入していましたが、任意継続で加入後は、全額自己負担となります。 収入によって多少前後はありますが、会社に勤めていた頃のおおよそ2倍の金額の保険料が必要となります。 また、任意継続を行う場合は、退職日の次の日から20日以内に手続きをしなければならず、保険期間も最大2年間までしか加入することができません。 国民健康保険組合とは、医師や美容師、建設業、税理士、弁護士、芸能人など特定の職種で働かれている方が対象となります。 また、業種によっては、加入条件もあり、自分が加入する組合の要項を確認してみましょう。 国民健康保険組合の保険料は、組合によって異なりますが、どれだけ収入が増えようが一律です。 収入が増えるほど、国民健康保険と比べると大きなメリットが得られます。 しかし、国民健康保険と同様に扶養家族がいる場合は、家族の保険料も負担しなければなりませんので注意が必要です。 家族が健康保険に加入している場合、その扶養に入ることができます。 「扶養に入る」とは、被保険者の配偶者や兄弟姉妹、子、孫、の収入で被保険者の生計がなされている状態のことを指します。 扶養に入る場合、個人での健康保険料を負担する必要がなくなるため、保険料を抑えることができます。 しかし、扶養は被保険者の年間所得が130万円未満の場合に適用されますので、年間の所得が130万円を超える場合は、注意が必要です。 参照:)フリーランスが加入すべき「保険」とは? 低コストでリスクに備える方法 フリーランスと会社員の保険の大きな違いは、「社会保険」の手厚さです。 社会保険とは、医療保険や年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険を指し、会社員は労働者として、公的な費用負担が発生した場合は、一部控除されます。 しかし、フリーランスになると会社員ほどの社会保険を受けることができなくなります。 労災保険と雇用保険に加入することができなくなり、事故に遭った際の治療費や仕事がなくなった時の保障はありません。 そのようなことに対する備えは民間保険で備えなければならず、その分も費用が発生してしまいます。 フリーランスは働き方が会社員と比べ自由になりますが、その代償は少なからずあるということを覚えておかなくてはなりません。 下記にフリーランスが加入可能な国民健康保険組合を記載しました。 しかし記載したのはほんのごく一部です。 加入をご検討されている方は、自分の業種や加入条件などを確認の上、申し込む必要があります。 また、国民健康保険と保険料等を比較いただき、割高にならないようにご注意ください。 国民健康保険組合は「組合」になりますので、同種の事業・業務の従事者を組合員として認定します。 そのため、組合側から定期的に事業の確認を求められることがあります。 フリーランスが国民健康保険組合に加入し、様々な事業を展開している場合、自身の業務が各種組合に該当するかどうかも常に確認しておきましょう。 参照:)東京都国民健康保険団体連合会 国民健康保険の保険料は、先述したように各自治体が運営しているため、基本的な計算方法が同じでも各自治体によって料率が異なります。 基本的な計算方法は、前年度の所得や配偶者と子の有無などによって決まります。 詳細は各自治体のホームページを確認してみましょう。 国民健康保険は、医療分保険料・支援分保険料・介護分保険料の3つから構成されており、3つの要素には、それぞれ所得割額と均等割額があります。 所得割額とは、基準所得金額×保険料率で計算され、基準所得金額の計算方法は、年間所得金額から基礎控除を差し引いた金額で表されます。 均等割額とは、被保険者×保険料率で計算されます。 一例ではありますが、新宿区に住んでいる30歳男性、独身(妻子なし)、昨年度の所得は300万円という方の国民健康保険料を計算してみましょう。 新宿区のホームページによると、以下の表のように料率が決められております。 算定基礎額とは、基準所得金額にあたるものです。 早速以下の手順で国民健康保険料を計算していきましょう! 年間所得-基礎控除48万円(合計所得金額2,400万円以下) ②医療分保険料を計算する 医療分保険料=所得割額+均等割額 ③支援分保険料を計算する 支援分保険料=所得割額+均等割額 ④介護分保険料を計算する 介護保険料は、世帯に40~64歳までの方のみ払わなければならず、今回はいないため、0円となります。 合計:②218,476円+③73,932円+④0円=292,408円 この合計金額は年間の国民健康保険料となりますので、月平均で表すと、約24,367円となります。 目安となりますが、この金額を聞いてどう感じたでしょうか。 高いと感じられた方に少しでも費用を抑える方法2つをお伝えさせていただきます。 先述したように国民健康保険料を運営しているのは、各自治体となります。 各自治体の財政状況等により、料率は決められておりますので料率が低い地域に引っ越すのが手っ取り早いでしょう。 今日では働き方も十人十色、場所を選ばなくなってきました。 フリーランスで活動される方は、居住地も1つのポイントになります。 フリーランスの場合、国民健康保険よりも自分の生活にあった保険に加入することで費用を抑えられることがあります。 前職の健康保険の任意継続や国民健康保険組合への加入、家族の扶養に入るという選択肢があり、自分に合った健康保険を選択することが大切です。 それぞれにメリットとデメリットがありますので自分で内容を十分理解し、考えてみましょう。 組織に所属していれば気にもしなかったこと、フリーランスではそれをそのままにしておくと大惨事になる可能性があります。 仕事中の事故や情報漏洩、納期遅延による損害などフリーランスの場合は、個人で解決しなければなりません。 もし莫大な損害が発生した場合は、個人で解決することは極めて困難になります。 時代の需要に合わせ、民間保険でもフリーランス向けの保険サービスがありますので、チェックしておくに越したことはありません。 ここでは検討すべき一部民間保険の種類を紹介させていただきます。 フリーランスにとって、一番と言っていいほどの心配事は、病気やけがなどで働けなくなり収入が途絶えてしまうことでしょう。 国民健康保険には、会社員の健康保険とは違い、傷病手当金がありません。 傷病手当金とは、病気やけがなどで連続する3日間を含み4日以上働けなくなった場合に現金が支給される制度です。 フリーランスは万が一の事態に備え、働けなくなった場合の備えが必要になります。 今日では、日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人が死亡しています。 大病を患ってしまうのは、フリーランスにとっても大きなリスクとなります。 がんの民間保険の中には、がんと診断された際に一時金を受け取り、治療費や生活費に充てることできるものもあるため、生活や治療に余裕を持つことができます。 がん保険を選ぶ際は診断時に一時金が受け取れるかどうか確認してみましょう。 フリーランスで活動していると予期せぬことでトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。 予期せぬトラブルとは、思いがけなく発生してしまった納期遅延による損害や情報漏洩が起きてしまった場合の損害賠償などです。 現代では情報漏洩に対する賠償は多大になることもあります。 そこで検討したいのが、フリーランス協会に加入することで付帯される損害賠償保険です。 賠償責任を問われ、多大な請求を受ける前にリスクヘッジとして加入しておくことも1つの手と頭の片隅に入れておきましょう。 参照:)フリーランスが知るべき保険の話。社会保険・民間保険、入るべきなのは? 保険に加入せず活動(生活)することは、極めて困難です。 日本は、「国民皆保険制度」で何かしらの保険に加入しなければならないというルールが定められております。 これまでの内容を振り返り、自分に適した保険を考えてみましょう! 今回は、フリーランスの保険事情について、解説しました。 フリーランスで活動することは会社員とは大きく違い、保険のみならず、自らの意思で選択しなければならないことが多くあります。 また、国民健康保険を選んだ際に支払う保険料については、抑えられるのであれば、抑えられるに越したことはありませんよね。 国民健康保険の保険料は、自治体によって変わりますので、自分の前年度の所得をもとに保険料が安い自治体に引っ越すのも1つの手です。 万が一に備え、自分の生活にあった保険を選択してみましょう。 フリーランスの人には案件さがしのコンタクトアースマッチングがおすすめです。 最新の高単価案件を見逃したくない方はこちらからかんたん10秒の無料会員登録! ✔全案件が完全リモート/高単価の案件多数 100万円以上の案件が80%以上
● 世帯主と加入者(家族)のマイナンバーカードもしくは通知カード
● 本人確認書類
● 国民健康保険証(世帯の中で、国民健康保険の加入者がいる場合)2.前職の健康保険の任意継続
3.国民健康保険組合(国保組合)
4.家族の扶養
フリーランスと会社員の保険の違い
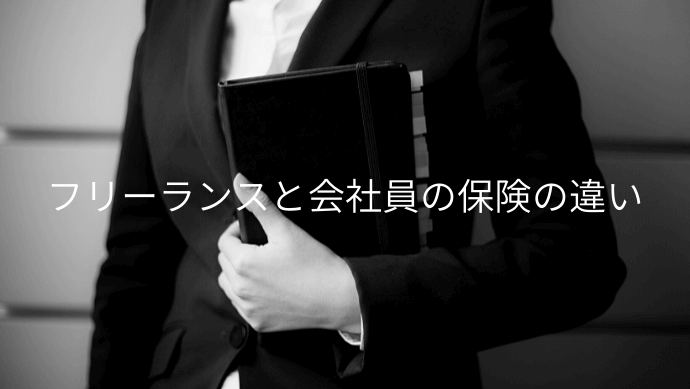
業種別のフリーランスが加入可能な国民健康保険組合とは
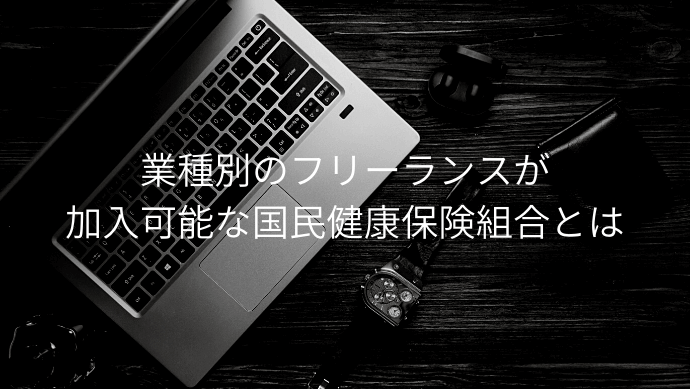
医師系
北海道医師国民健康保険組合
青森医師国民健康保険組合
弁護士・税理士系
東京都弁護士国民健康保険組合
関東信越税理士国民健康保険組合
建設系
全国土木建設国民健康保険組合
神奈川県建設業国民健康保険組合
薬剤師系
東京薬剤師国民健康保険組合
三岐薬剤師国民健康保険組合
美容・理容系
東京美容国民健康保険組合
東京理容国民健康保険組合
芸能・美術系
文芸美術国民健康保険組合
東京芸能人国民健康保険組合
食品系
東京食品販売国民健康保険組合
大阪府食品国民健康保険組合
フリーランスの国民健康保険料はいくらか?費用の抑え方

医療分
支援金分
介護分
所得割額
38,800円×世帯加入者数
13,200円×世帯加入者数
17,000円×世帯加入者のうち40~64歳の加入者数
均等割額
世帯加入者全員の算定基礎額×7.13%
世帯加入者全員の算定基礎額×2.41%
世帯加入者のうち40~64歳の算定基礎額×2.05%
賦課限度額
63万円
19万円
17万円
300万円-48万円=252万円(基準所得金額)
38,800×1+2,520,000×7.13%=218,476円
13,200×1+2,520,000×2.41%=73,932円国民健康保険料の料率が低い自治体に引越しをする
自分の生活にあった健康保険に加入する
フリーランスが加入できる他の保険3選
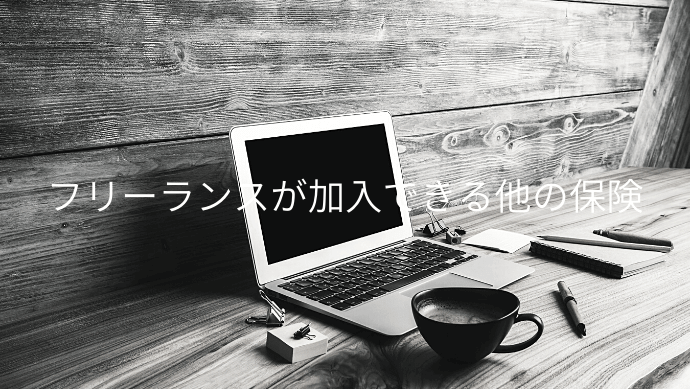
1.就業不能保険
2.がん保険
3.損害賠償保険
保険に加入せずフリーランスをすることは可能?

フリーランスの保険事情についてのまとめ
フリーランスの方へ無料登録はこちら

✔週1回~フルタイムまで自分で稼働日数を選べます。
✔働きたい時にすぐ働けて、最短2日で仕事に入れます。
✔本サービスの仕事はDX案件に特化