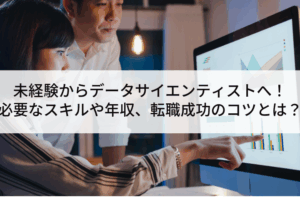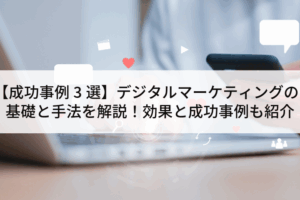本記事では医療DXの仕組みやその鍵を握るマイナ保険証によってできるようになることを解説します。
2024年12月2日から紙の保険証の発行が終了し、注目度の高まるマイナ保険証で何が変わるのか知りたい方は最後までご覧ください。
医療機関などにおける業務効率化や、より良い医療提供のために医療DXが進められており、マイナ保険証は診療情報などを医療機関同士が共有するために重要な役割を果たします。
マイナ保険証がもたらすメリットと、普及に向けた課題を順番に見ていきましょう。

マイナ保険証とは
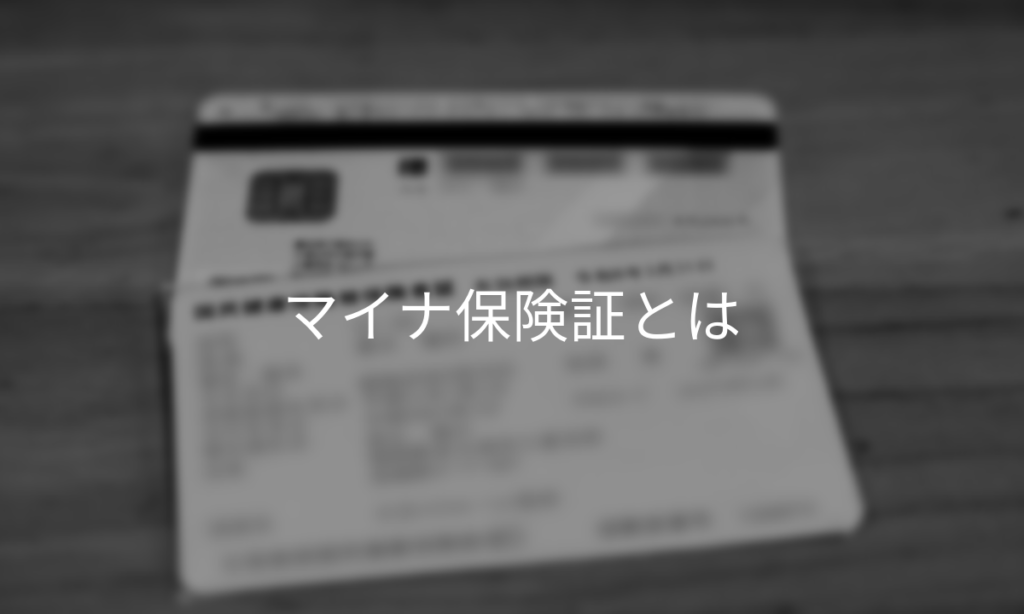
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを医療機関や薬局で利用できるようにしたものです。
受付で顔認証付きカードリーダーを利用して、マイナンバーカードによる本人確認を行います。
従来よりも、正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得などを行えるため、より良い医療提供につながります。
既にマイナンバーカードを持っている場合、マイナポータルや医療機関・薬局などでマイナンバーカードの健康保険証利用を申請すれば利用可能です。
マイナンバーカードを持っていない人でも、従来の健康保険証を用いて有効期限までの間、最長1年間は利用できます。
ただし、紙の健康保険証は令和6年12月2日を持って新規発行を終了したため、今後はマイナ保険証への移行が進んでいくでしょう。
参照:
・「マイナンバーカードの健康保険証利用について」厚生労働省
・「マイナンバーカードの健康保険証利用」デジタル庁
マイナポータルとは
マイナポータルとは、マイナンバーカードを用いて行政手続きが行えるオンライン窓口です。
パソコンやスマートフォンからアクセスでき、自分の情報確認なども行えます。
これまで市役所などに問い合わせないと申請や確認ができなかった情報がオンラインで行えるようになったため、手続きの効率化に寄与しています。
また、公金受取口座の登録・変更や、確定申告の電子手続き、引越しにかかる手続きなどを行うことも可能です。
公金の受け取りについては、緊急時の給付金だけでなく、税額還付や児童手当なども受け取れます。
金融機関の口座番号などを国に提供しますが、預貯金残高などの情報を知られることはありません。
参照:
・「行政手続きをオンラインで」デジタル庁 マイナポータル
・「よくある質問:公金受取口座登録制度について(総論)|デジタル庁」デジタル庁
医療DXとは

医療DXとは、医療などの各段階で発生するデータをクラウドなどを通して、共有・利用することで、国民へ質の高い医療提供や業務効率化を目指す取り組みです。
具体的には、次の5つの実現を目標としています。
● 切れ目なく質の高い医療等を効率的に提供すること
● 医療機関等の業務効率化
● システム人材等の有効活用
● 医療情報の二次利用を行うための環境整備
これらを実現する上で、手続きのオンライン化の土台となるマイナ保険証は、医療DXにおける基盤といえるでしょう。
ここからは医療DXが目指す3つの取り組みについて解説します。
❷ 電子カルテ情報共有サービス
❸ 診療報酬改定DX
それぞれ順番に見ていきましょう。
参照:
・「医療DXについて」厚生労働省
・「医療DXの推進、マイナ保険証の利用及び電子処方箋の導入に関する状況について」厚生労働省
医療DXを推進するために、医療機関に対するインセンティブも設けられています。
医療DX推進体制整備加算について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
全国医療情報プラットフォーム
全国医療情報プラットフォームとは、各機関で保管されている患者の医療情報を一元的に管理することを目的とした、国が構想するシステムです。
医療機関や介護施設、自治体などでバラバラに保管している医療情報をクラウド上に集約することで情報共有が容易になります。
具体的には、電子カルテ情報や予防接種情報、レセプト情報、介護情報などを共有します。
医師だけでなく患者も自分の情報をどこからでも確認可能です。
また、健康保険証だけでなく公費受給者証のオンライン資格確認も可能なため、受給者証を忘れたり、期限切れの受給者証を持参したりした患者への対応もスムーズになります。
従来は一時的に健康保険単独での会計を行い、後に再精算していたため、医療事務の大きな負担となっていました。
他にも、院内のシステムに公費受給者番号などの情報を手入力で登録する際の誤登録のリスクもなくなるため、業務改善効果が期待されます。
参照:
・「全国医療情報プラットフォームとは?2つのサービスや医療DXを解説」株式会社スタメン TUNAG
・「全国医療情報プラットフォームの役割とは」株式会社CBパートナーズ CBパートナーズ
電子カルテ情報共有サービス
電子カルテ情報共有サービスとは全国医療情報プラットフォームの仕組みの一つで、電子カルテ情報の共有が可能です。
電子カルテ情報共有サービスは主に3つの機能から成り立っています。
1つ目は、紹介状の送付サービスです。
紹介元の医療機関が登録した診療情報提供書や退院時サマリーを、患者の同意を受けて提供することで、紹介先の医療機関がオンライン上で閲覧できるようになります。
紹介状を紙媒体で患者が持参したり、FAXで送信したりする必要がなくなるため、患者の持参忘れ・紛失や、医療機関同士の連携ミスによる情報漏洩を防ぐことができます。
2つ目は、6情報閲覧サービスです。
6情報とは、傷病名・アレルギー・薬剤禁忌・感染症・検査・処方を指し、これらを本人や全国の医療機関が、原則患者の同意を得た上で閲覧できるようになります。
一般外来では、同意を得てから閲覧できる期間も定めており、利便性向上だけでなく、情報がみだりに閲覧されないようにもされています。
3つ目は、健診文書閲覧サービスです。
医療機関から直接各種健診文書をオンライン資格確認システムに登録できるため、その結果を他の医療機関や患者がオンライン上で確認できるようになります。
また、患者が自分の健康状態を確認し、健康習慣の改善につなげたり、医療機関受診時に検診結果を忘れたときも確認できたりするといったメリットがあります。
参照:
・「マイナ保険証移行のタイムリミット迫る!「医療DX」が国民にもたらすメリットとは」エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 docomo business
・「電子カルテ情報共有サービス」厚生労働省
・「全国医療情報プラットフォームの役割とは」株式会社CBパートナーズ CBパートナーズ
診療報酬改定DX
診療報酬改定DXとは、2年に一度改定される診療報酬にともなう、短期間での作業が求められる報酬改定業務と、システムにロジックを組み込む負担を軽減するための仕組みです。
診療報酬の制度は複雑で、発表後に通知される疑義解釈などから理解する必要があります。
しかし、短期間で内容を読み解きシステムに組み込むのは医療機関やシステムベンダーの大きな負担になっていました。
そこで、厚生労働省やデジタル庁などが共同して共通算定モジュールを作成し、モジュールを更新するだけで診療報酬改定にかかるシステムの更新作業が完了することを目指しています。
これによって、医療現場やシステムベンダーの負担を軽減することが期待されています。
参照:
・「診療報酬改定DXとは?その概要と医療機関にもたらすメリット・デメリットを徹底解説します!」株式会社メドレー CLINICS
・「【2024年最新版】診療報酬改定DXと医療DX推進体制整備加算の全貌を解説」日本インターシステムズ株式会社 INTER
マイナ保険証のメリット
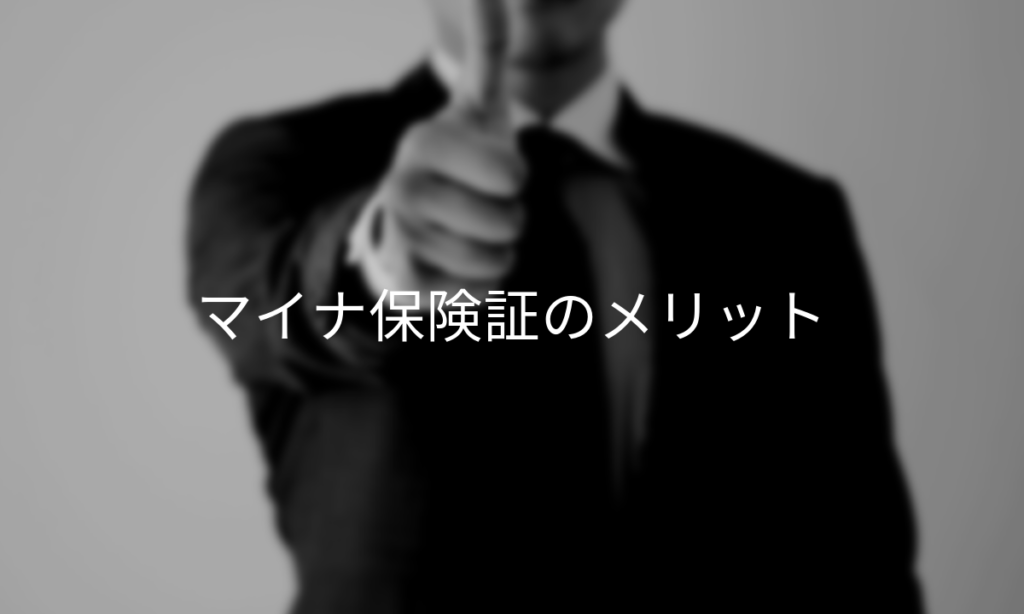
次にマイナ保険証を利用するメリットを解説します。
マイナ保険証によって、患者や医療機関にどのようなメリットがあるのか参考にしてみてください。
それぞれ順番に見ていきましょう。 これまでは医療費控除を受ける際、その年に支払った医療費の領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告を行う必要がありました。 また、申告のもととなった領収書は自宅で5年間保存しなければなりませんでした。 しかし、マイナ保険証を利用して受診していれば、マイナポータルからe-tax(国税電子申告・納税システム)に情報連携されるため、データの自動入力が可能です。 また、マイナポータル上に医療費通知情報が保存されるため、自宅に領収書を保管する必要もなくなります。 ただし、確定申告時に必要な1年間の医療費通知情報は原則翌年の2月9日に一括取得できるようになります。 そのため、確定申告の受付期間が始まる直前まで医療費の自動入力はできません。 他にも、医療費控除は通院にかかる交通費なども控除対象となりますが、マイナポータルに反映されるのは保険診療の費用のみです。 通院費や自費診療費用などは自分で申告する必要があり、その領収書も5年間保存しなければなりません。 同様に、医療費控除は自分と生計を一にする家族の医療費についても控除対象にできますが、自分のマイナポータルで確認できるのは、自分の医療費のみです。 家族分も合算して申告する場合、マイナポータル上で代理人設定をする必要があります。この場合、合算される家族もマイナンバーカードを取得していなければなりません。 参照: マイナ保険証を利用することで、2021年8月以降の過去1ヶ月〜5年間で処方された薬の情報や診療情報を自分のマイナポータルで確認できます(電子処方箋対応の医療機関や薬局の場合、即時〜5年前まで)。 また、過去5回分までの健診情報も確認可能です。 ただし、本人同意がなければ閲覧できないようになっているため、みだりに他人に医療情報を知られることはありません。 参照: マイナンバーカードの健康保険証利用について手続きが完了している場合、転職・退職などに伴う、健康保険証としての再登録は不要です。 保険者や福祉事務所への加入・喪失手続きは従来通り必要ですが、新しい健康保険証が手元に届くのを待たなくて良くなります。 これまでは、転職などをした際に次の健康保険の「資格確認書」が発行されるまでは、一時的に保険料の全額負担が必要でした。 マイナ保険証であれば、健康保険の加入・喪失手続きが完了していればすぐに利用できるため、保険料を全額負担せずに医療を受けられます。 参照: マイナ保険証を医療機関の窓口で利用すると、限度額情報が連携されるため、高額療養費制度利用時の一時負担がなくなります。 これまでは役所で事前手続きを行わないと、一時的に全額負担しなければならないこともありました。 しかし、マイナ保険証を利用すれば一時的に負担しなくてもよくなるため、経済的な負担が軽減されます。 マイナ保険証を医療機関の窓口で利用する際、診療・薬剤情報や特定健診などの結果を提供することに同意すると、医師や薬剤師から総合的な処方や診察が受けられます。 重複する投薬の回避や薬の飲み合わせの考慮、検診結果を踏まえた判断などが行われるため、より精度の高い医療を受けることが可能です。 また、救急車で搬送される際にも、患者の口頭による説明ではなく、正確な診療・薬剤情報を基に搬送先の選定や必要な検査の準備が行えるようになります。 参照: マイナ保険証を薬局や医療機関などで利用する際は、顔認証で受付を行います。 これによって、従来よりも正確な本人確認ができ、過去の医療情報の提供についての同意も適切に行うことができます。 本人確認と本人同意を経てからしか過去の医療情報を提供できないため、みだりに自分の情報は閲覧されません。 また、医療情報を提供することで、前述のように様々な情報を踏まえた医療判断を行ってもらえるようになります。 参照: 続いてマイナ保険証によって今後できるようになることを解説します。 前章で解説したもの以外にもマイナ保険証には様々な機能が実装される予定です。 どのような機能が今後追加されていくのか、知りたい方は参考にしてみてください。 それぞれ順番に見ていきましょう。 マイナンバーカードが保険証と医療費助成受給者証、診察券を兼ねるようになることで、マイナ保険証のみで病院の受付が可能になります。 医療機関や薬局においても、保険証や診察券情報の手入力を不要にし、情報が自動連携によって入力内容を確認する負担も軽減することを目指しています。 マイナンバーカードに機能が集約されることで、診察券忘れを防げるようになるため、患者にとってのメリットも大きいでしょう。 参照:「診察券・医療費助成の受給者証とマイナンバーカードの一体化に係る医療機関・薬局システム事業者向け説明会」デジタル庁 マイナンバーカードで予防接種などを受けられるようにし、接種履歴や検診結果もスマートフォンから確認できるようになることを目指しています。 受診者が予防接種や母子保健(乳幼児健診・妊婦健診)において、問診票や予診票を事前にスマートフォンを通じてマイナポータルに記入することで、マイナンバーカードのみで受診が可能になります。 マイナ保険証のみで完結するため、受診者の手続きも簡略化されるでしょう。 また、既にこの取り組みを選考して行っている自治体もあります。 参照:「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」デジタル庁 マイナ保険証をスマートフォンに搭載することで、マイナンバーカードを持ち歩かなくても医療機関を受診できるようになります。 マイナンバーカードや健康保険証を持ち歩く必要がなくなり、診察券などとの一本化と併せればスマートフォンだけで受診可能です。 医療機関や薬局の受付手順としては、まず患者が顔認証付きカードリーダーの画面上でスマートフォンによる手続きを行う旨を選択します。 次に新たに設置されたリーダーにスマートフォンをかざします。 このとき、Androidでは暗証番号の入力、iPhoneでは生体認証による本人確認が行われる予定です。 最後に顔認証付きカードリーダーの画面上で医療情報提供の同意に関するボタンをタッチすれば手続きが完了します。 これによって、マイナ保険証の利用率向上が期待されています。 本機能はAndroid・iPhoneともに2025年春を目処にリリースされる予定です。 参照: 最後にマイナ保険証の課題を3つ解説します。 メリットも多いマイナ保険証ですが、普及に際して課題も山積しています。どのような課題があるか順番に見ていきましょう。 それぞれ詳しく解説します。 2024年12月におけるマイナ保険証の利用件数は、厚生労働省の調査によると6,220万件でした。 マイナンバーカード保有者に占めるマイナ保険証の利用状況は約40%のため、決して高い水準とは言えません。 医療機関別の利用率で見ても約13〜28%の間であり、特に個人のクリニックにおいて低い利用率となっています。 参照: マイナンバーと健康保険証の紐づけを誤り、他人の情報と結びつけられていた事案があったことによる国民の不信感も普及を妨げています。 保険者や行政機関などにおいてマイナンバーの紐づけ作業をアナログな方法で行っていたことが主な要因とされ、2023年5月までに7,372件の誤りが判明しています。 国はこれを受けてデータの全件チェックを行っていますが、国民の不安を拭いきれていないことが利用率の低さにつながっているかもしれません。 参照: 厚生労働省の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算にかかるインターネット調査」では、マイナ保険証を利用するメリットについて、認知している人の割合は2〜3割程度しかいないことがわかりました。 メリットを認知している世代には偏りがなく、全体的に知られていないことが伺えるため、周知不足も要因の一つと考えられます。 そのため、医療機関などにマイナ保険証の利用を推進する周知ポスターを掲示することを診療報酬加算の要件に設定しています。 参照: 今回はマイナ保険証やマイナポータルが医療DXにおいて、どのようなメリットをもたらすのか、課題と併せて解説しました。 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることで、医療機関だけでなく患者にも多くのメリットがあります。 患者のカルテ情報などを基に広い視点から医療が行われる上に、情報漏えいがないよう本人確認と同意がなければ原則情報の閲覧ができないように構築されています。 利用率の低さや国民の不安など一定の課題はありますが、今後もマイナ保険証に様々な機能が実装されることが見込まれるため、医療DXに関する開発案件も増えていくでしょう。 Contact EARTH matchingでは、官公庁や医療機関などからの高単価案件も多く掲載しています。 DX化を推進する案件を探しているフリーランスエンジニアの方は無料エキスパート登録をして案件をご覧になってみてください。 ✔高単価案件多数
● 受診歴・特定健診情報がいつでも確認できる
● 健康保険の切れ目をなくしやすい
● 高額療養費制度利用時の一時負担がなくなる
● 診療・薬剤処方の共有による適切な処方が受けられる
● 受付がスムーズになる確定申告の医療費控除が簡単になる
・「マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~」厚生労働省
・「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」厚生労働省
・「医療費控除を受ける方へ」国税庁 令和6年分確定申告特集
・「過去何年分の医療費通知情報が閲覧可能でしょうか。」デジタル庁 マイナポータルよくあるご質問受診歴・特定健診情報がいつでも確認できる
・「よくある質問~マイナ保険証について~令和7年2月版」厚生労働省
・「過去何年分の医療費通知情報が閲覧可能でしょうか。」デジタル庁 マイナポータルよくあるご質問
・「過去何年分の診療・薬剤情報、薬剤情報が閲覧可能でしょうか。」デジタル庁 マイナポータルよくあるご質問健康保険の切れ目をなくしやすい
・「マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)とは?メリット・デメリット、登録方法をわかりやすく解説」フリー株式会社 freee
・「既にマイナンバーカードでの保険証等利用登録は完了していますが、就職や転職、退職等により、健康保険証等が変更になりました。手続きは必要ですか。」デジタル庁 マイナポータルよくあるご質問
・「転職や退職をしましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録が必要でしょうか。」デジタル庁 マイナポータルよくあるご質問
・「マイナンバーカードの保険証は転職したら再登録が必要?空白期間も解説」東京海上日動あんしん生命 マネコミ!高額療養費制度利用時の一時負担がなくなる
診療・薬剤処方の共有による適切な処方が受けられる
・「マイナンバーカードの健康保険証利用」デジタル庁
・「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」デジタル庁受付がスムーズになる
・「マイナンバーカードの健康保険証利用について」厚生労働省マイナ保険証で今後できるようになること
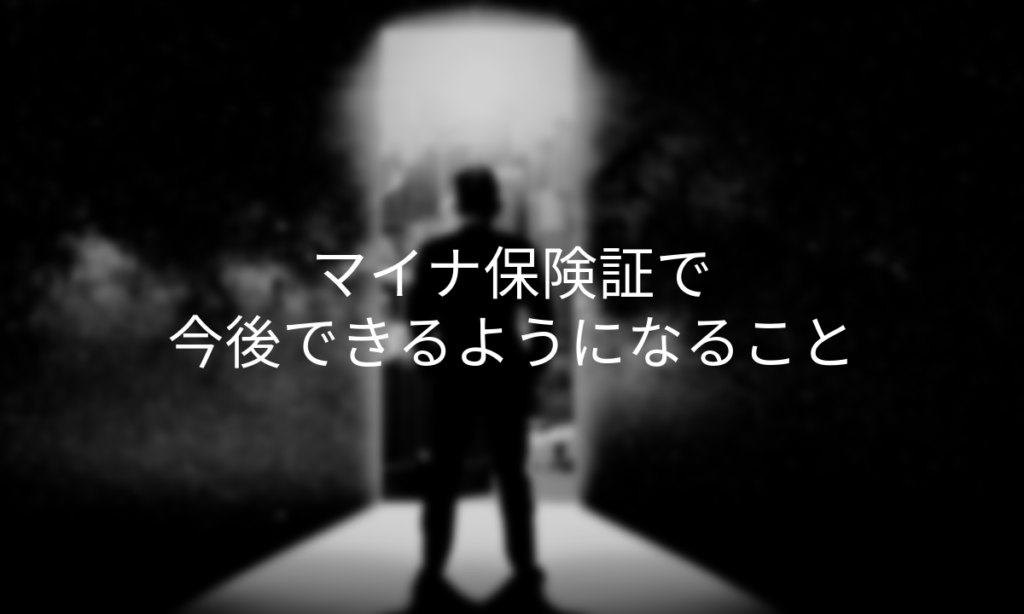
● 予防接種・母子保健の一本化
● スマートフォンによる受診保険証・受給者証・診察券の一本化
予防接種・母子保健の一本化
スマートフォンによる受診
・「カンタン!便利!マイナンバーカードの健康保険証利用」厚生労働省
・「マイナ保険証、スマホ搭載は25年春にも 厚労省公表」株式会社日本経済新聞社 日本経済新聞
・「”スマホ化”対応の医療機関支援 マイナ保険証の普及促進で―厚労省検討」 株式会社時事通信社 JIJI.COMマイナ保険証の課題
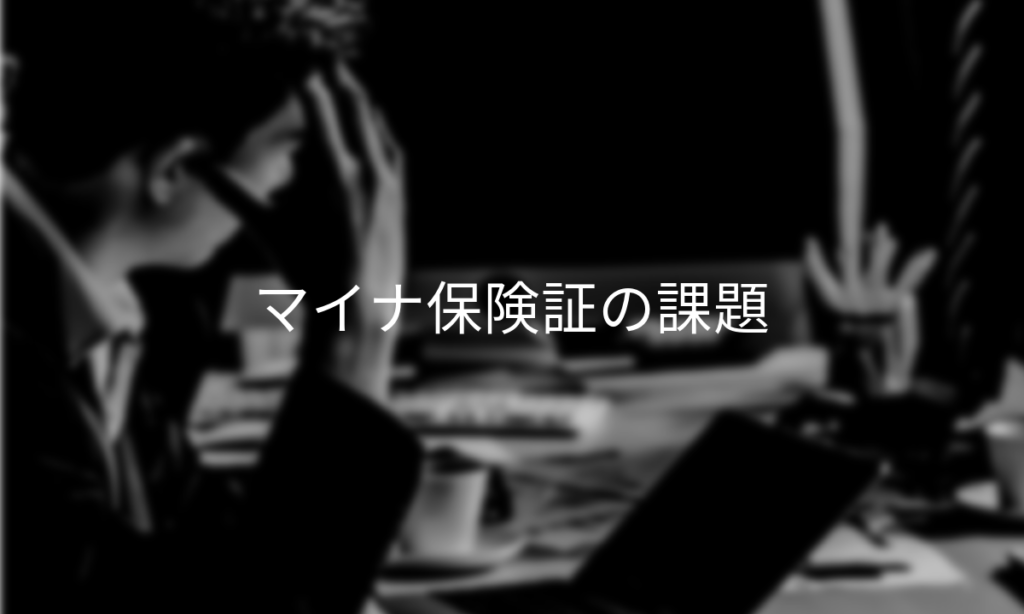
● マイナンバーの紐付け誤り
● メリットがあまり知られていない利用率の低さ
・「マイナンバーカードの健康保険証利用について」厚生労働省
・「マイナ保険証の利用促進等について」厚生労働省マイナンバーの紐付け誤り
・「マイナンバーを巡る諸問題と対応について」デジタル庁
・「1万人調査に見るマイナ保険証への賛否」株式会社三菱総合研究所メリットがあまり知られていない
・「医療情報・システム基盤整備体制充実加算にかかるインターネット調査について(結果報告)」厚生労働省
・「オンライン資格確認に関する周知素材について」厚生労働省まとめ
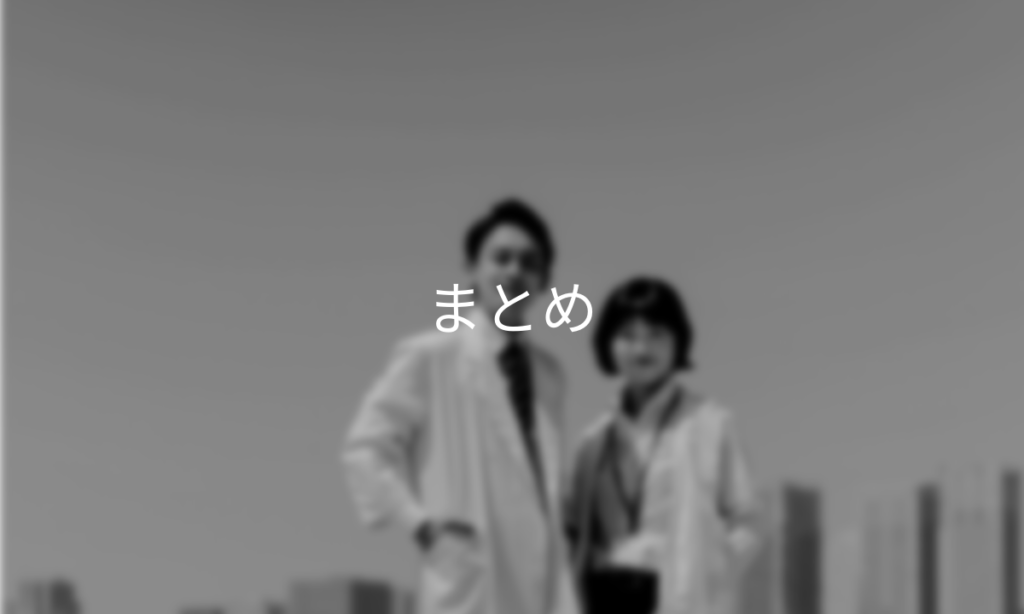
フリーランス向けのフルリモート案件をお探しの方へ

150万円以上の案件が80%以上、200万円以上も!
✔フルリモート案件多数
リモートで完結するDX・戦略案件が見つかる
✔上場企業や優良企業から直接スカウトが届く
簡単なプロフィールを登録し、あとはスカウトを待つだけ

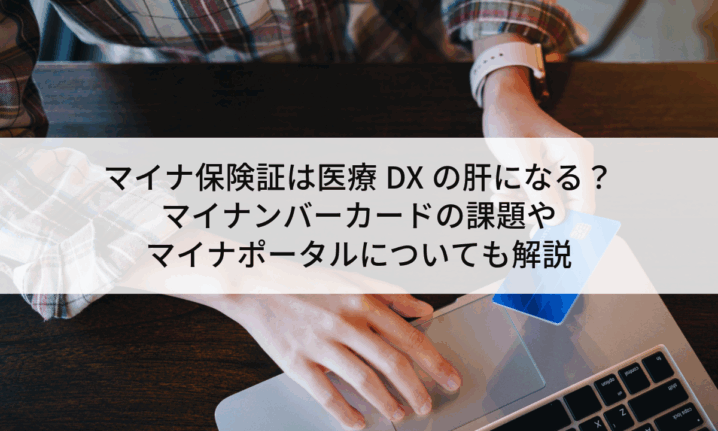
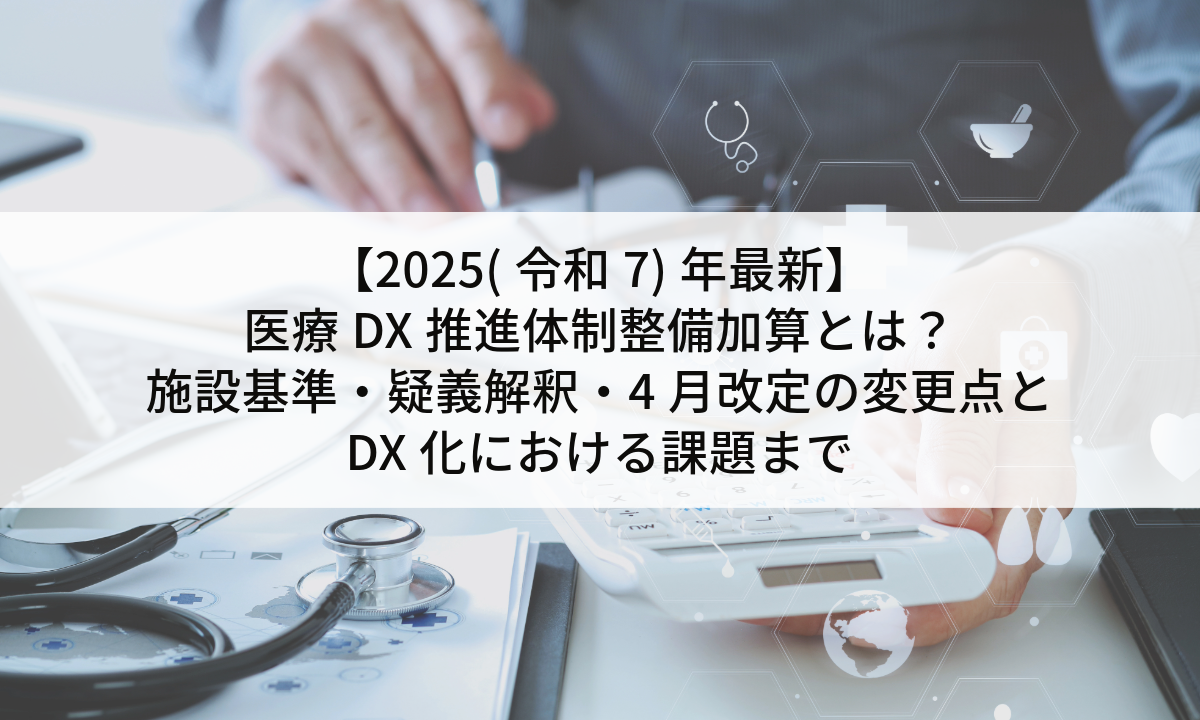
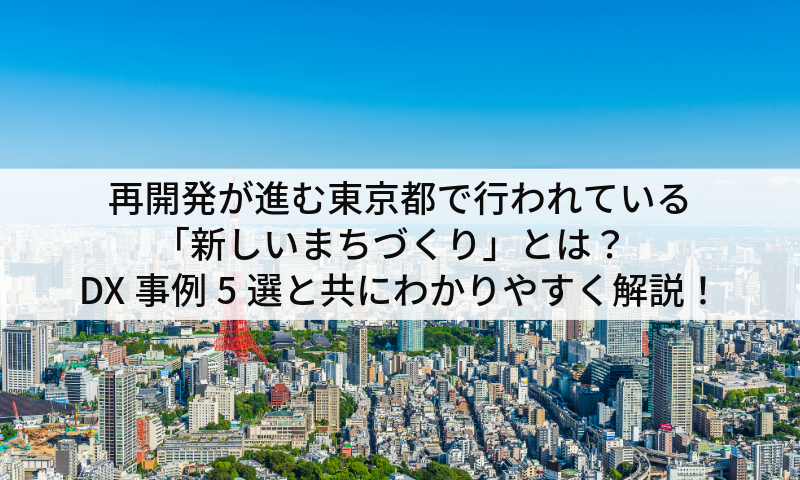

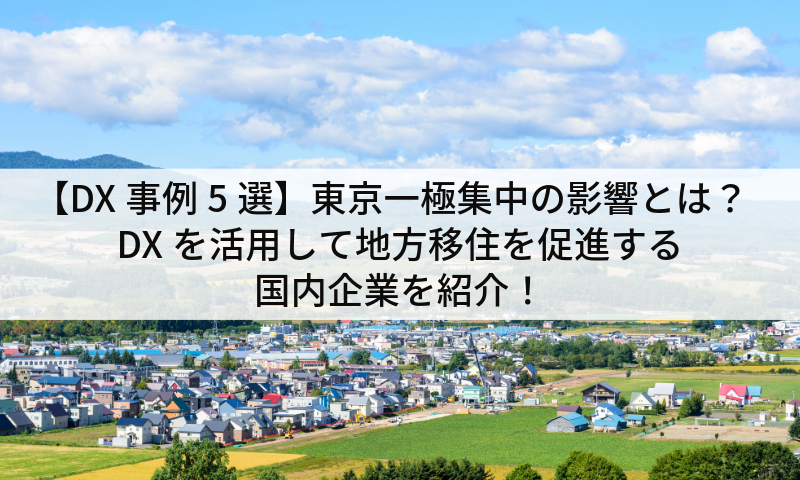

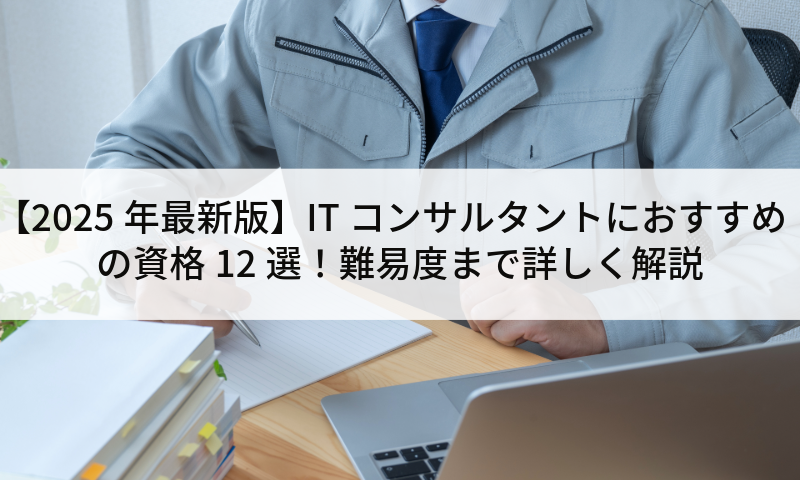
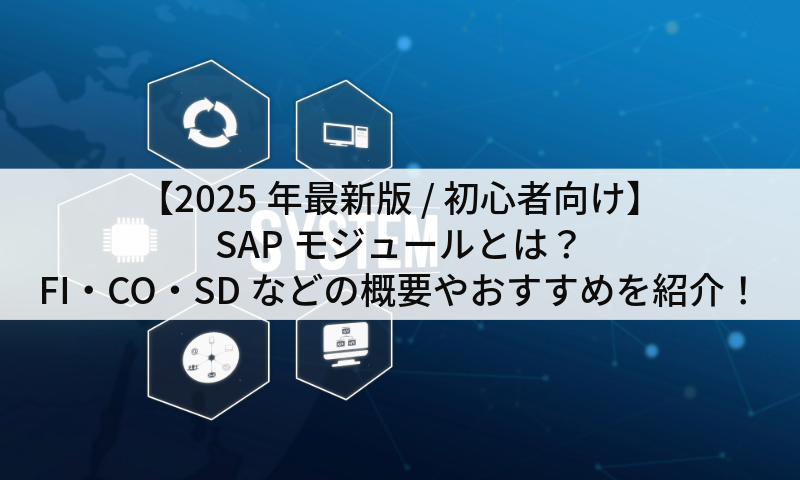
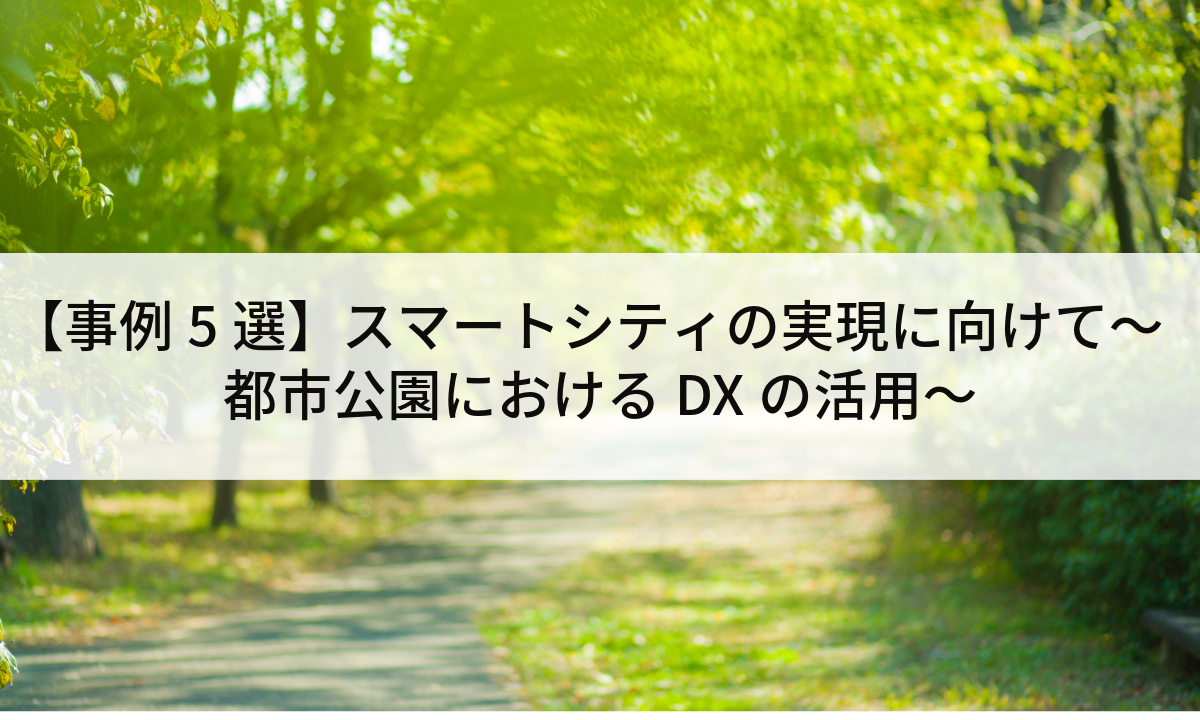
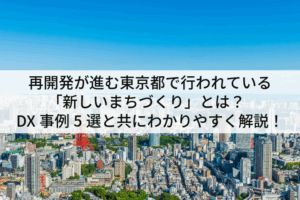
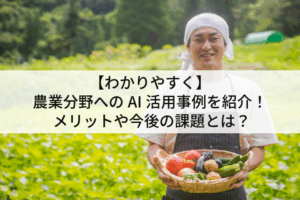

-2-300x200.png)